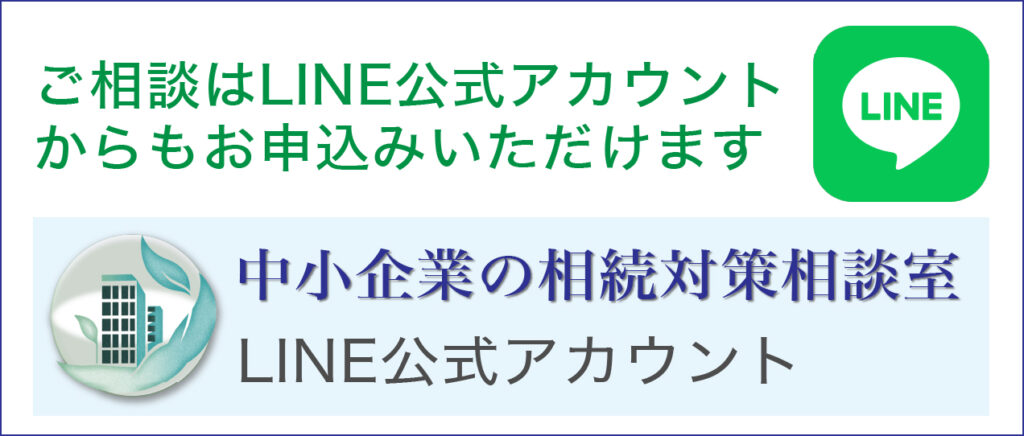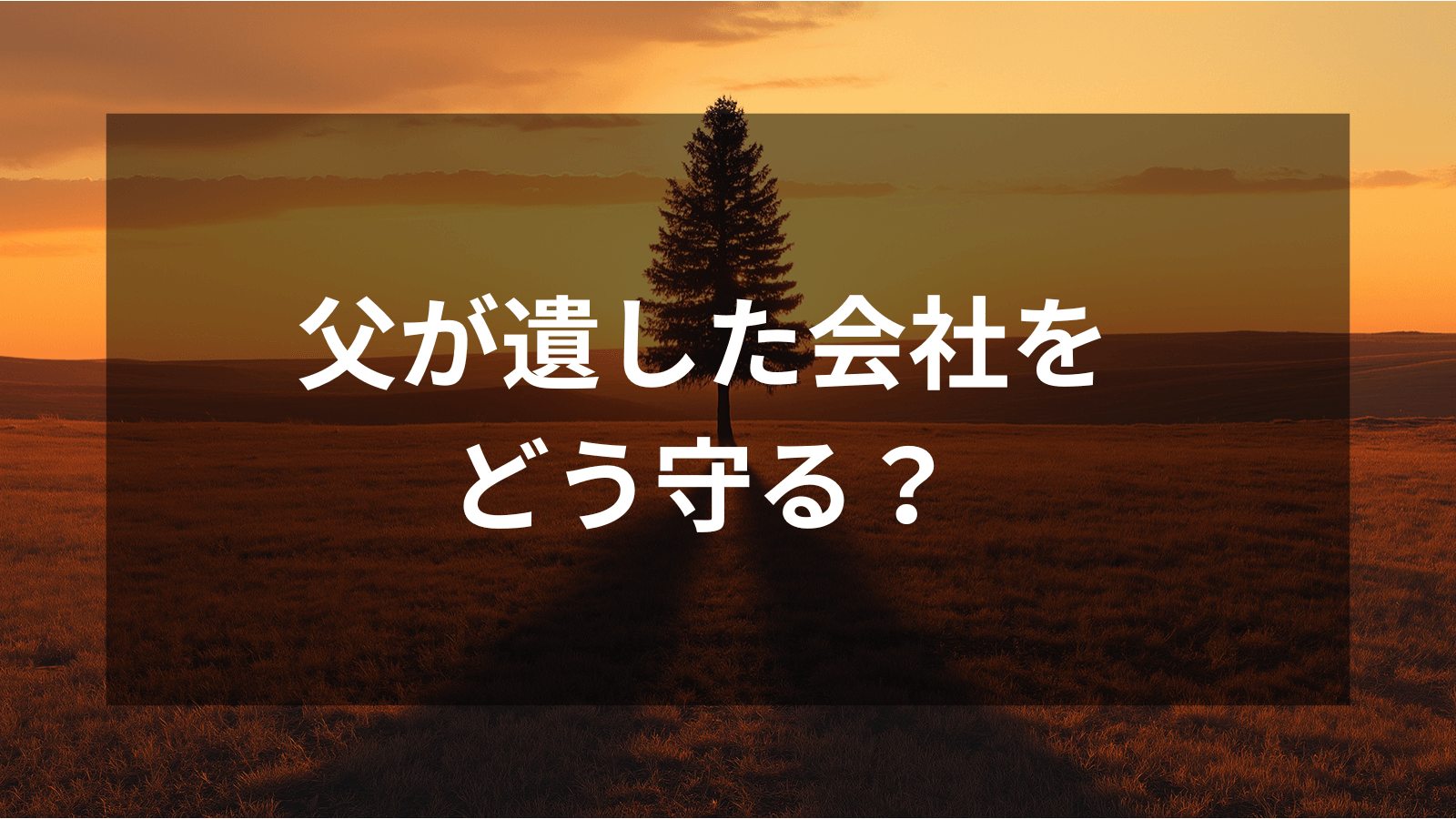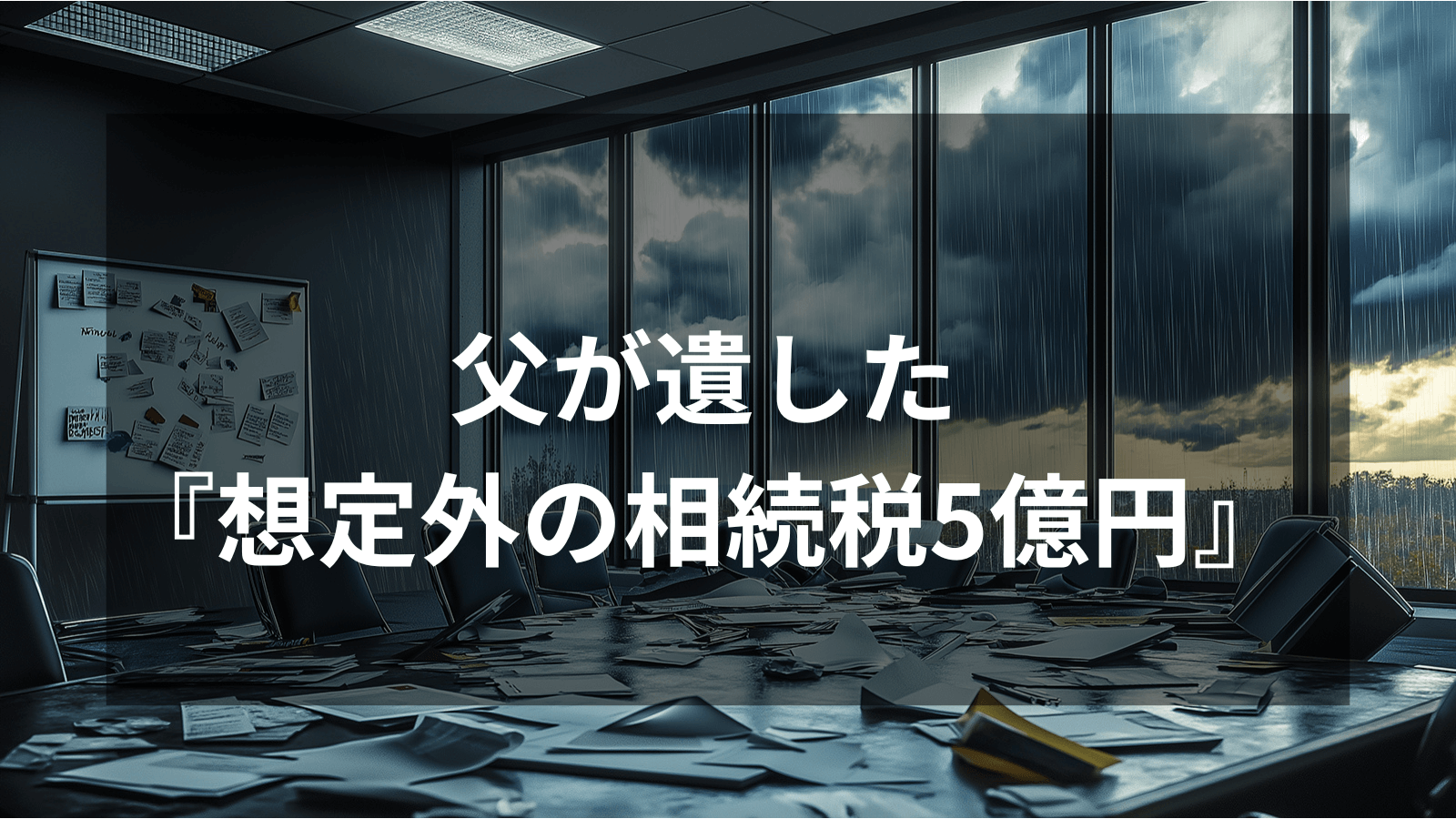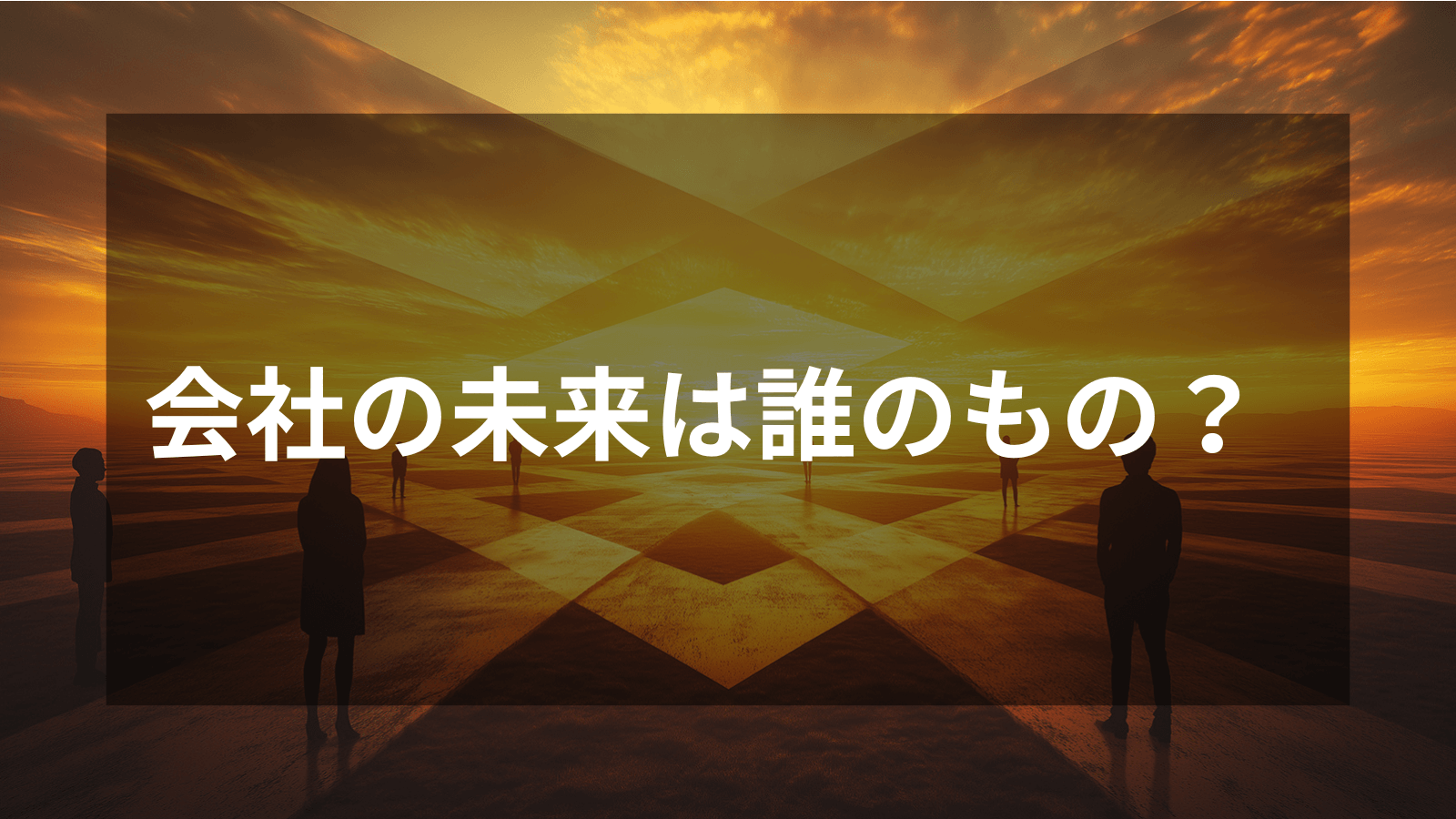<第三回>家族の安心から考える会社の相続対策
第三回:老後の生活プランなしに事業承継はできない
はじめに:社長の終活が事業承継の成功を左右する
これまで2回にわたって、相続税と保証債務という家族が直面するリスクについて解説してきました。最終回となる今回は、経営者と家族の「老後の生活」について考えます。
多くの社長は会社の事業計画は詳細に作成しますが、自分自身の引退時期や引退後の生活については「まだ先のこと」として後回しにしがちです。しかし、社長自身の老後の生活プランが明確でないと、安心して事業を後継者に託すことができませんし、後継者が本気で承継しようとは考えません。それは後継者の育成にも大きな影響を与えます。
今回は、なぜ社長の生活プランが事業承継に不可欠なのか、具体的な事例を交えながら解説いたします。
社長が引退できない理由
多くの中小企業の社長が引退を躊躇する最大の理由は、引退後の生活資金への不安です。
よくある不安要素
• 引退後に年金だけで生活費が賄えるか
• 医療費や介護費用の不安
• 自分が亡き後の配偶者や家族の生活保障
中小企業特有の問題
• 個人資産の多くが事業に投入されており、老後の生活資金に回せない
• 経営者の退職金制度が整備されておらず、資金の裏付けがない
• 個人資産を会社に貸し出していても、他人に貸し出すような利益が得られない
経営への過度な執着
• 「自分がいないと会社が回らない」という思い込み
• 後継者の不在及び後継者への過度な期待
• 経営以外の生きがいが見いだせない
責任感
• 従業員の雇用への責任
• 取引先との関係維持
• 家族の生活保障
引退時期が決まらないことで起こる問題
事例1:運送会社C社の場合
社長の状況
• 社長(72歳)、息子(45歳・専務取締役)
• 会社:従業員20名、年商3億円
• 社長は「もう少し頑張る」と言い続けて5年経過
何が起こったか
社長は体力的にきつくなってきましたが、引退後の生活資金に不安があり、引退時期を決められずにいました。息子は後継者として期待されていましたが、いつ社長が引退するのか分からないため、自分の人生設計ができません。
家族と会社への影響
• 息子は45歳になっても「社長代理」のような立場
• 重要な意思決定は依然として父親が行う
• 息子のモチベーション低下と転職の検討
• 従業員から「いつまで続くのか」という不安の声
• 取引先からも事業承継への懸念
結果
結局、社長が75歳の時に軽い脳梗塞で倒れ、急遽事業承継を行うことになりました。準備不足のまま承継したため、会社の業績が一時的に悪化し、数名の従業員が退職しました。
事例2:製造業D社の場合
社長の状況
• 社長(68歳)、長男(40歳・取締役)、長女(38歳・他社勤務)
• 会社:従業員25名、年商4億円
• 社長は「老後の資金が心配」と引退を先延ばし
何が起こったか
社長は引退後の生活費として月30万円が必要と計算しましたが、年金だけでは月15万円程度しか見込めません。不足分を補うための貯蓄も、事業資金として使ってしまい十分ではありませんでした。
問題の深刻化
• 長男は40歳になっても重要な権限を与えられない
• 取引先から「後継者は大丈夫か?」という声
• 長男の妻から「いつまで待てばいいのか」という不満
• 社長自身も体力の限界を感じながら決断できない
解決への道筋
専門家のアドバイスにより、以下の対策を実施。
• 退職金と企業年金の設計
• 会社からの賃料収入の確保
• 段階的な役員報酬の移行計画
• 5年後の完全引退スケジュールの設定
老後の生活資金の確保方法
社長の引退後の生活を支える資金は、主に「退職金」「年金」「会社からの継続収入」の3つの柱で構成されます。
退職金については、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」で算定し、一括支給が税務上有利ですが、会社の資金負担を考慮して分割支給や年金型との組み合わせも検討すべきでしょう。また、社長の万一のことを考えて、会社受取の生命保険を退職金の原資として準備することも必要です。
年金に関しては、厚生年金と共に生命保険会社等で販売している年金型の保険を検討し、老後の資金の設計とすることができます。
後継者の育成と権限移譲
事業承継の成功は、段階的な権限移譲にかかっています。多くの失敗例では、社長が突然すべてを任せて後継者が混乱し、業績が悪化しています。
それぞれの事情により、後継者への移譲の計画は、個別具体的に検討するべきですが、プロセスの例としては、1~2年目に日常業務の権限を移譲し、部門責任者として従業員との信頼関係を構築させることから始まり、3~4年目には月次業績管理や重要取引先との関係構築を任せ、5年目に代表権を移譲するやり方もあります。
後継者のモチベーション維持には、明確なスケジュールの提示が不可欠です。「いつまでに何を習得すべきか」「どの時点で権限移譲されるか」を明示し、役職と責任に見合った報酬や待遇改善を行うことで、後継者は将来への希望を持って取り組むことができます。
家族全体のライフプラン
社長の引退プランは、家族全体の将来に大きく影響します。特に配偶者の生活設計は重要で、社長より長生きする可能性を考慮した老後資金の準備や、医療・介護費用、住居確保の計画が必要です。二次相続対策として、配偶者が相続する財産の管理方法や、配偶者の判断能力低下への備え、家族信託の活用も検討すべきでしょう。家族信託とは、財産を信頼できる家族に託して管理してもらう制度で、認知症などで判断能力が低下した場合でも、あらかじめ定めたルールに従って財産の管理が可能になります。
また、後継者以外の家族への配慮も忘れてはいけません。事業用資産と個人資産を明確に区別し、後継者以外の相続人への公平な配慮を行い、遺言書によって明確な意思表示をすることが重要です。定期的な家族会議を開催し、各家族の希望や不安を把握し、専門家を交えた説明を行うことで、家族全体の合意形成を図ることができます。
専門家との連携による総合的プラン
複雑な事業承継を成功させるためには、複数の専門家との連携が不可欠です。税理士は退職金の税務設計や相続税対策との整合性、事業承継税制の活用をサポートします。行政書士は遺言書の作成や家族信託契約の設計を担当し、司法書士は不動産の名義変更や担保関係の整理、各種登記手続きを行います。これらの専門家が連携することで、法的・税務的に最適な承継プランを実現できます。
成功する事業承継のポイント
早期の準備開始
事業承継で最も重要なのは早期の準備開始です。60歳頃から本格的な準備を始めても決して早すぎることはありません。後継者の育成には最低5年、制度設計や資金準備にも相当な時間が必要だからです。
一度にすべてを変えるのではなく、段階的に実行し、各段階での効果を測定しながら柔軟に計画を修正していくことが成功の鍵となります。「まだ元気だから大丈夫」という先延ばしは、結果的に家族全体を困らせることになります。
家族の理解と協力
透明性のあるコミュニケーション
• 計画の共有と説明
• 定期的な進捗報告
• 家族の意見や不安への対応
専門家による客観的説明
• 第三者の視点による説明
• 感情的にならない議論
• 法的・税務的な正確性の確保
まとめ:安心の引退が成功の事業承継を生む
社長の老後の生活プランは、単に個人的な問題ではありません。それは事業承継の成功を左右する重要な要素です。
重要なポイント
- 引退後の生活資金を具体的に計算する
- 退職金や年金を知り、適切に設計する
- 会社からの継続収入を確保する
- 明確なスケジュールで権限移譲を進める
- 後継者のモチベーションを維持する
- 家族全体のライフプランを考える
専門家と連携して総合的に準備する
「まだ元気だから大丈夫」「そのうち考える」という先延ばしは、結果的に家族全体を困らせることになります。社長自身が安心して引退できる環境を整えることが、後継者にとっても、従業員にとっても、そして家族にとっても最良の結果をもたらします。
事例、人物、企業等の設定はフィクションです。
監修者

宮澤 博
税理士・行政書士
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、 お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、 他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。
無料相談のご予約・お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
(ソレイユ総合窓口となります)
0120-971-131
営業時間/平日9:00~20:00まで
※電話受付は17:30まで