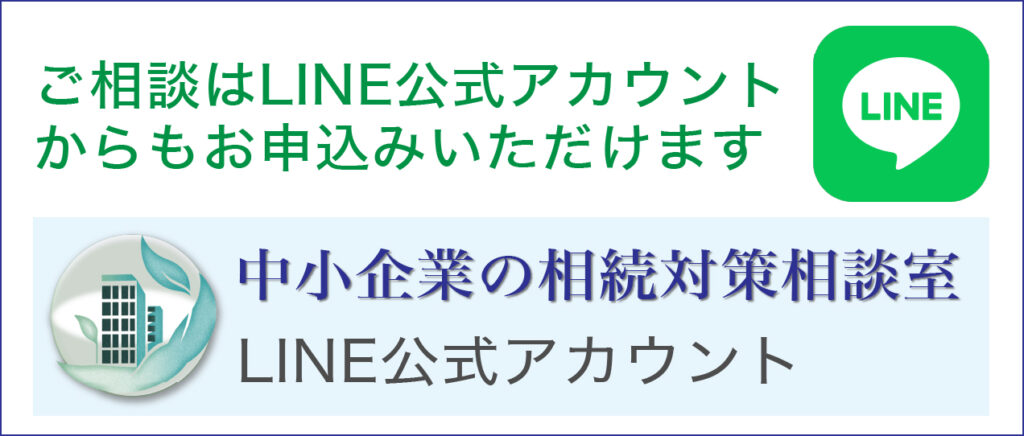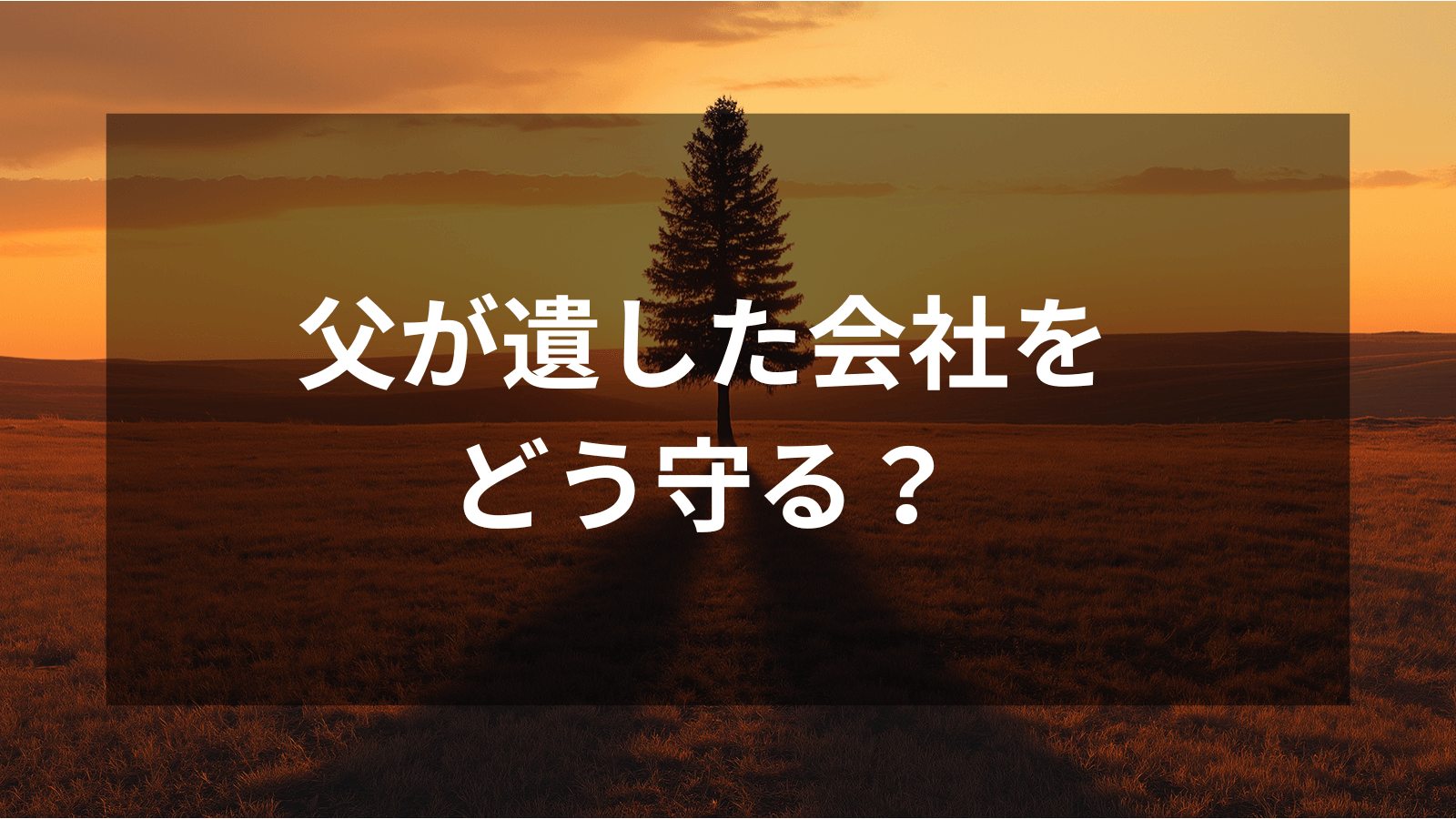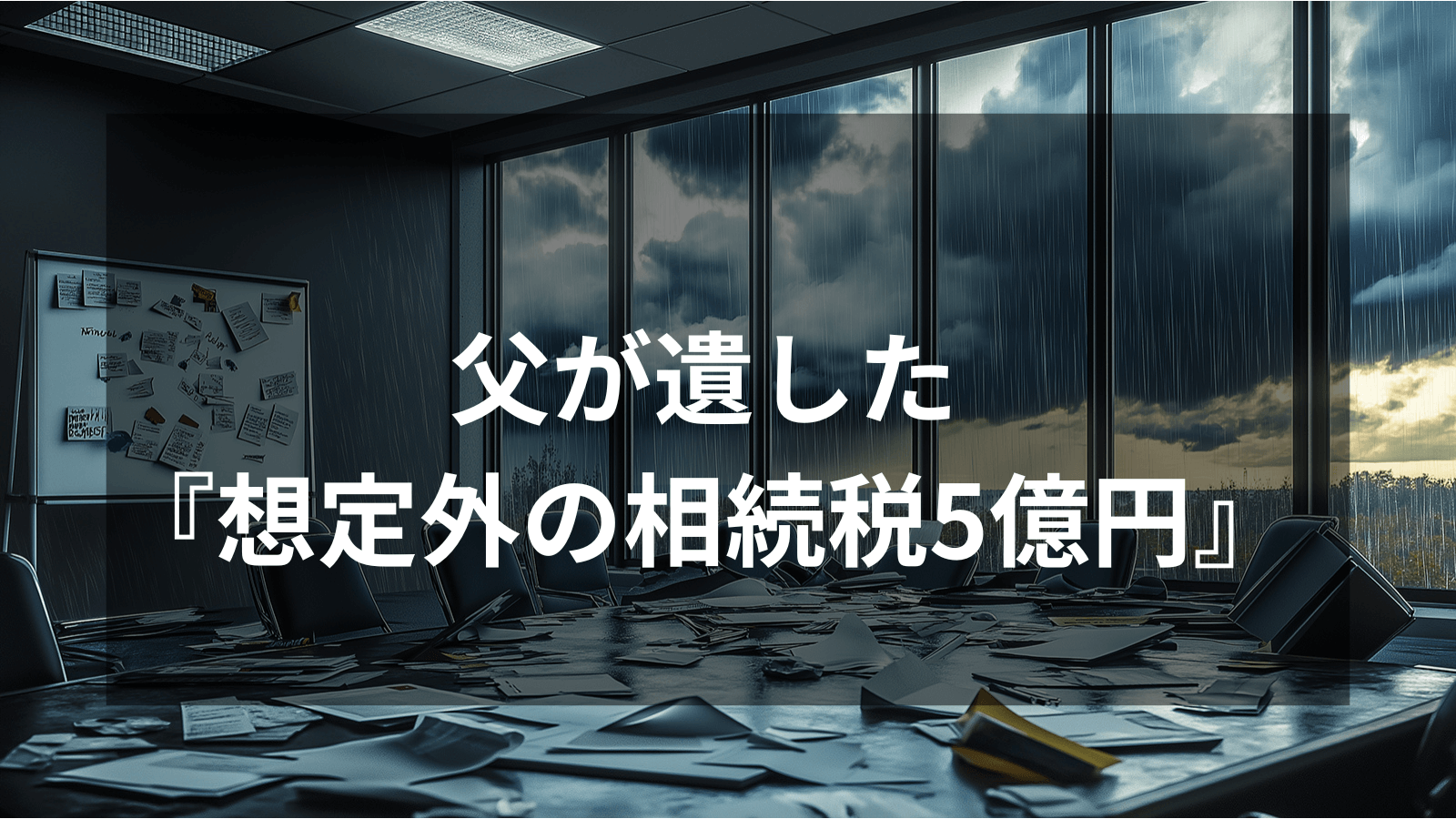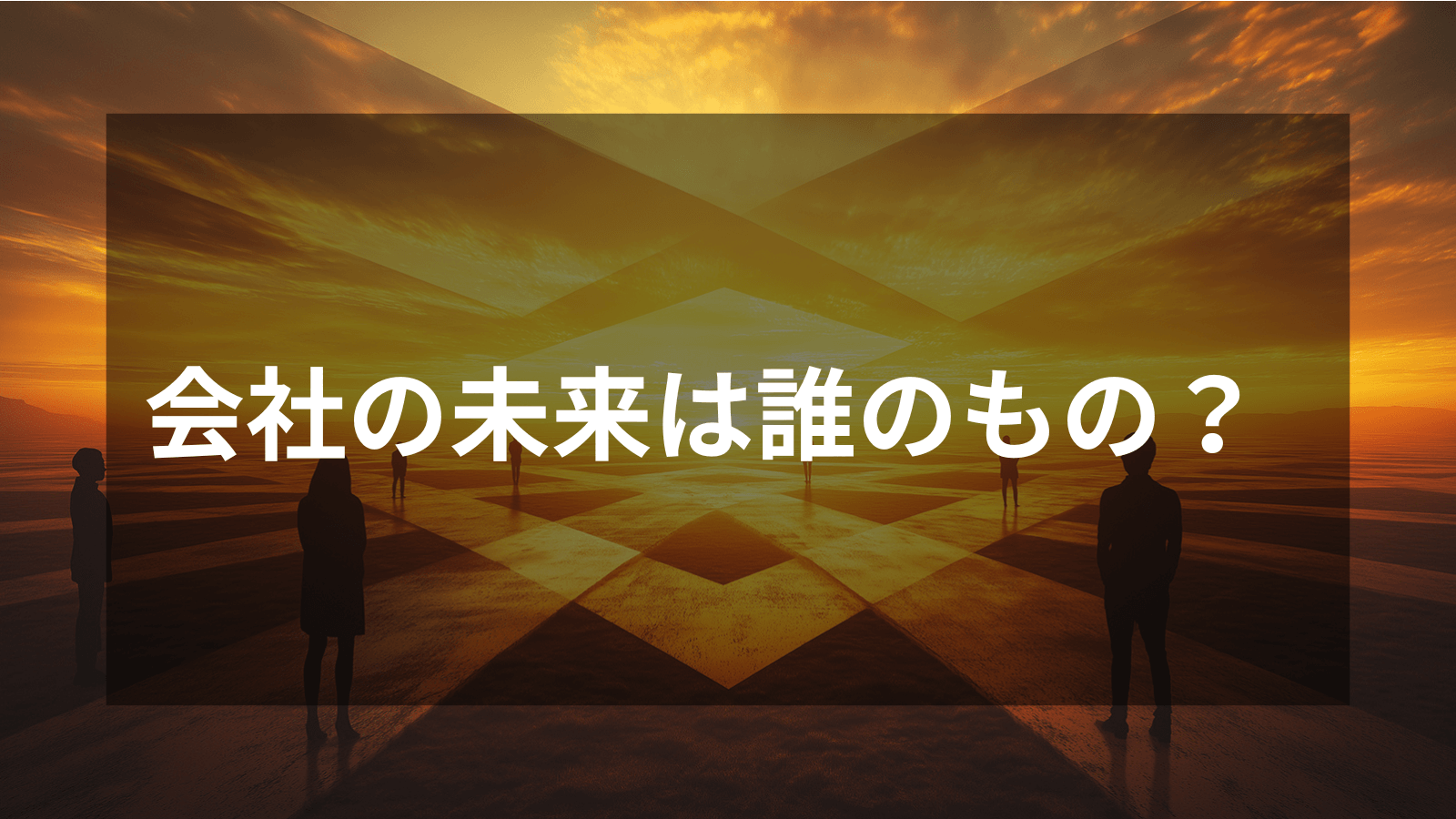<第一回>家族への財産の遺し方
財産の全体像把握と相続税の基礎知識
はじめに
中小企業の経営者にとって、家族への財産の遺し方は単なる相続問題ではありません。事業の継続、従業員の雇用維持、そして家族の生活保障という三つの要素が複雑に絡み合う重要な課題です。多くの経営者が「まだ先のこと」と考えがちですが、適切な準備なくしては、築き上げた財産も事業も、期待通りに次世代に引き継ぐことは困難です。
本シリーズでは、中小企業経営者が知っておくべき財産の遺し方について、実践的な観点から3回に分けて解説します。第1回となる今回は、相続対策の出発点となる「財産の全体像把握」と「相続税の基礎知識」について詳しく説明します。
今回は、なぜ社長の生活プランが事業承継に不可欠なのか、具体的な事例を交えながら解説いたします。
自身の全体財産を正確に把握する
なぜ財産の把握が重要なのか
「自分の財産がいくらあるかわからない」という経営者の方は意外に多いものです。特に中小企業の場合、個人財産と会社の財産が入り組んでいることが多く、全体像を正確に把握することが困難になっています。しかし、適切な相続対策を立てるためには、まず「何を」「どのくらい」「誰に」遺すのかを明確にする必要があります。
財産一覧表の作成方法
相続対策の第一歩として、以下の財産カテゴリーごとに一覧表を作成することをお勧めします。
1.現金・預金
• 普通預金・定期預金の残高
• 複数の金融機関に分散している場合はすべて記載
• 外貨預金がある場合は円換算額も併記
2.株式
• 自社株式:株数、評価額(後述の評価方法で算定)
• 上場株式:株数、時価総額
• 投資信託、債券等の有価証券
3.不動産
• 自宅、事業用不動産、投資用不動産
• 土地・建物それぞれの評価額
• 抵当権等の担保設定状況
4.生命保険
• 契約者、被保険者、受取人の関係
• 保険金額、解約返戻金額
• 相続税評価上の取扱い
5.その他の財産
• 会員権(ゴルフ会員権等)
• 自動車、宝石、美術品
• 貸付金、売掛金等の債権
相続税評価額の特徴と計算方法
財産を把握する際は、時価ではなく相続税評価額で計算することが重要です。相続税評価額は、実際の市場価格とは異なる評価方法を用いるため、財産の種類によって大きな違いが生じます。
不動産の相続税評価
土地の評価方法
・路線価方式:路線価が設定されている地域では、路線価×面積×各種補正率で算定
・倍率方式:路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額×倍率で算定
路線価は公示価格の約80%の水準に設定されているため、土地の相続税評価額は一般的に市場価格(実勢価格)の80%程度となることが多いです。
建物の評価方法
• 固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となる
• 固定資産税評価額は建築費の50~70%程度に設定されているため、建物の相続税評価額は一般的に市場価格より低くなる
相続税の軽減特例・評価上の特徴
・小規模宅地等の特例:自宅や事業用地について50~80%の評価減額
・借地権・底地の評価:権利が分離していることによる評価額の特徴
借地権:土地の利用権(通常、更地価格の60~90%程度)
底地:地主が持つ所有権(通常、更地価格の10~40%程度)
事例:不動産評価の実際
A社長の自宅土地建物
・土地:路線価20万円×300㎡ = 6,000万円
・小規模宅地等の特例(80%減)適用後:1,200万円
・建物:固定資産税評価額 1,500万円
・合計相続税評価額:2,700万円
・市場価格推定:約5,000万円
上場株式の相続税評価
上場株式は、相続開始時の時価で評価されますが、株価の変動リスクを考慮して複数の価格のうち最も低い価格を選択できます。
評価方法
- 相続開始日の終値
- 相続開始月の平均株価
- 相続開始前月の平均株価
- 相続開始前々月の平均株価
上記のうち最も低い価格を選択可能です。
自社株(非上場株式)の相続税評価
自社株の評価は最も複雑で、会社の規模や株主の地位により評価方法が異なります。
会社規模による区分
• 大会社:類似業種比準価額方式
• 小会社:純資産価額方式
• 中会社:上記の併用方式
評価額の目安
一般的に、自社株の相続税評価額は以下のような特徴があります。
• 利益が出ている会社:簿価純資産の1.5~3倍程度
• 不動産を多く保有する会社:時価純資産に近い水準
• 赤字会社:簿価純資産額程度
事例:自社株評価の実際
B社(従業員50名、年商10億円)の場合
・簿価純資産:5,000万円
・時価純資産:8,000万円(不動産含み益あり)
・年平均利益:3,000万円
・相続税評価額:約1億2,000万円
・社長保有割合:80%
・社長保有分評価額:9,600万円
現在の相続税額を知る
相続税の基礎控除額
令和6年現在の相続税基礎控除額は以下の通りです: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
法定相続人数別の基礎控除額
• 配偶者と子2人(計3人):4,800万円
• 配偶者と子1人(計2人):4,200万円
• 配偶者のみ(計1人):3,600万円
相続税率と計算方法
相続税は累進税率制を採用しており、税率は10%から最高55%まで段階的に上がります。
相続税速算表
| 課税価格 | 税率 | 控除 |
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
具体的な計算事例
C社長のケース
• 相続財産:1億5,000万円
• 法定相続人:配偶者、長男、次男(計3人)
• 基礎控除額:4,800万円
• 課税遺産総額:1億200万円
計算過程
・法定相続分での按分
o 配偶者:5,100万円
o 長男:2,550万円
o 次男:2,550万円
・各人の相続税額
o 配偶者:5,100万円×30%-700万円=830万円
o 長男:2,550万円×15%-50万円=332.5万円
o 次男:2,550万円×15%-50万円=332.5万円
相続税総額:1,495万円
活用できる税法特例
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産については、以下のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
• 1億6,000万円
• 配偶者の法定相続分相当額
小規模宅地等の特例
居住用や事業用の土地について、大幅な評価減が受けられます。
• 特定居住用宅地:330㎡まで80%減額
• 特定事業用宅地:400㎡まで80%減額
• 貸付事業用宅地:200㎡まで50%減額
事業承継税制
自社株の相続・贈与について、一定の要件を満たせば相続税・贈与税の納税が猶予されます。
• 一般措置:発行済株式総数の3分の2まで
• 特例措置:発行済株式総数の100%まで(令和9年まで)
財産把握における注意点
名義財産への対応
税務署は、名義だけ家族にしている財産(名義財産)について厳しくチェックします。以下の点に注意が必要です。
• 預金口座の実質的な管理者は誰か
• 株式の議決権は誰が行使しているか
• 不動産の固定資産税は誰が支払っているか
債務の把握も重要
相続財産からは債務も控除できるため、以下の債務についても正確に把握する必要があります。
• 金融機関からの借入金
• 個人保証している会社の債務
• 未払いの税金や社会保険料
• 買掛金、未払金
定期的な見直しの必要性
財産状況は時間の経過とともに変化します。少なくとも年に1回は財産一覧表を更新し、相続税の試算を行うことをお勧めします。
まとめ
第1回では、家族への財産の遺し方を考える出発点として、財産の全体像把握と相続税の基礎知識について解説しました。重要なポイントを整理すると
・財産の正確な把握が全ての出発点
o 現金・預金、株式、不動産、生命保険等を網羅的にリストアップ
o 相続税評価額での算定が重要
・相続税評価の特徴を理解する
o 不動産:市場価格の70~80%程度
o 上場株:4つの価格から最低値を選択
o 自社株:会社規模により評価方法が異なる
・現在の相続税負担を把握する
o 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人数
o 累進税率により税負担は大きく変動
・活用できる特例制度を知る
o 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例
o 事業承継税制等の適用可能性を検討
次回は、把握した財産を「どのように遺すか」という観点から、配偶者への財産の遺し方、事業承継、生前贈与の活用方法について詳しく解説します。適切な財産の遺し方を知ることで、税負担を最小限に抑えながら、家族の生活保障と事業承継を両立させる道筋が見えてくるでしょう。
事例、人物、企業等の設定はフィクションです。
監修者

宮澤 博
税理士・行政書士
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、 お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、 他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。
無料相談のご予約・お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
(ソレイユ総合窓口となります)
0120-971-131
営業時間/平日9:00~20:00まで
※電話受付は17:30まで