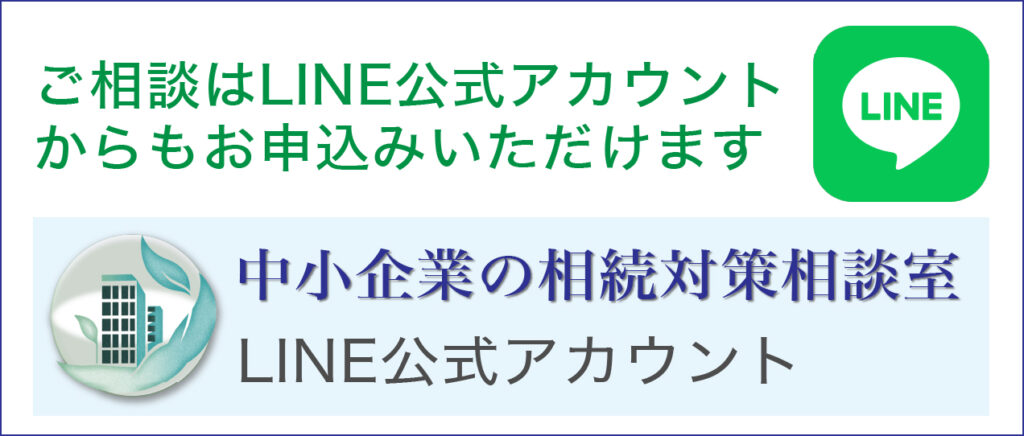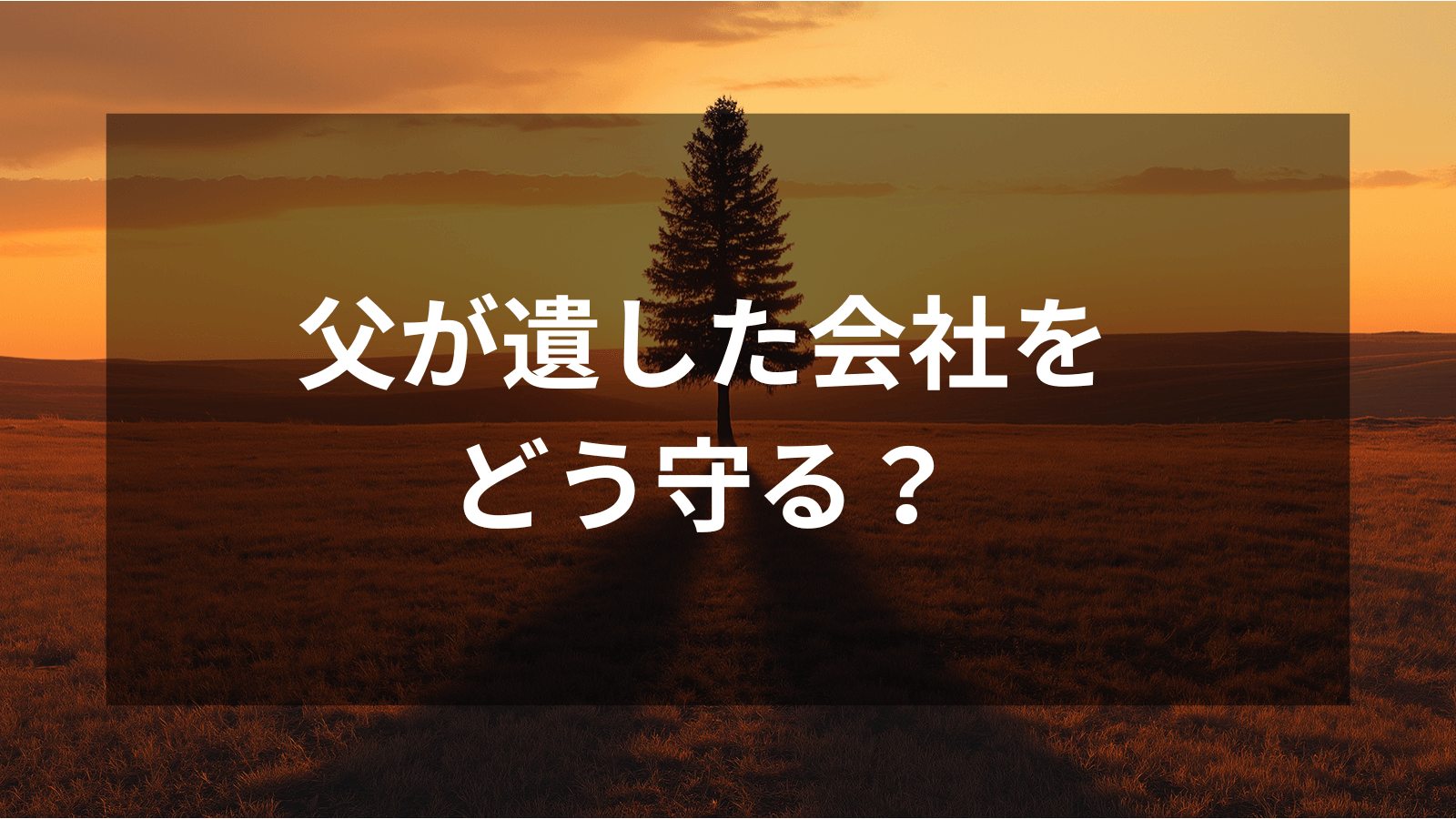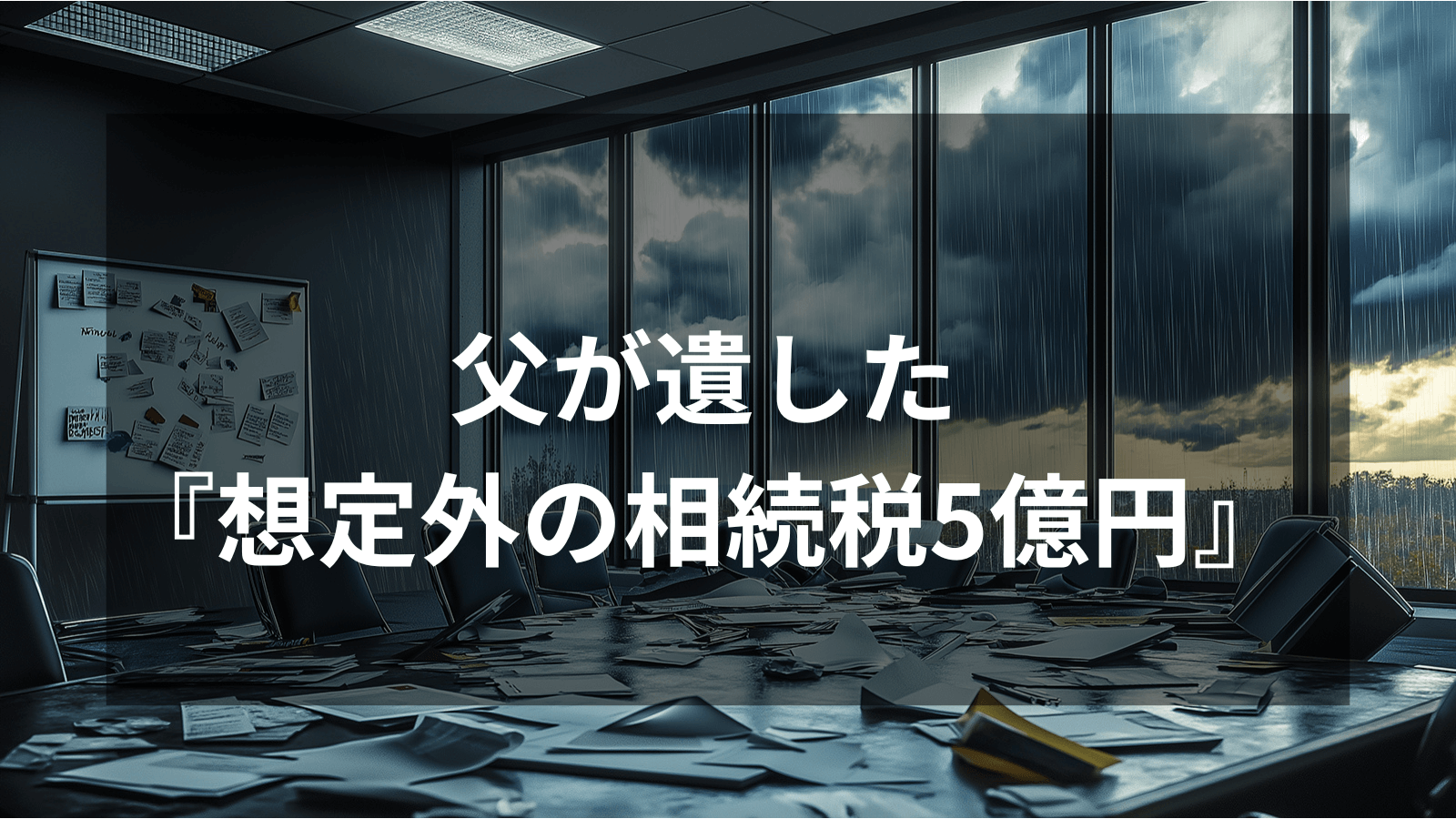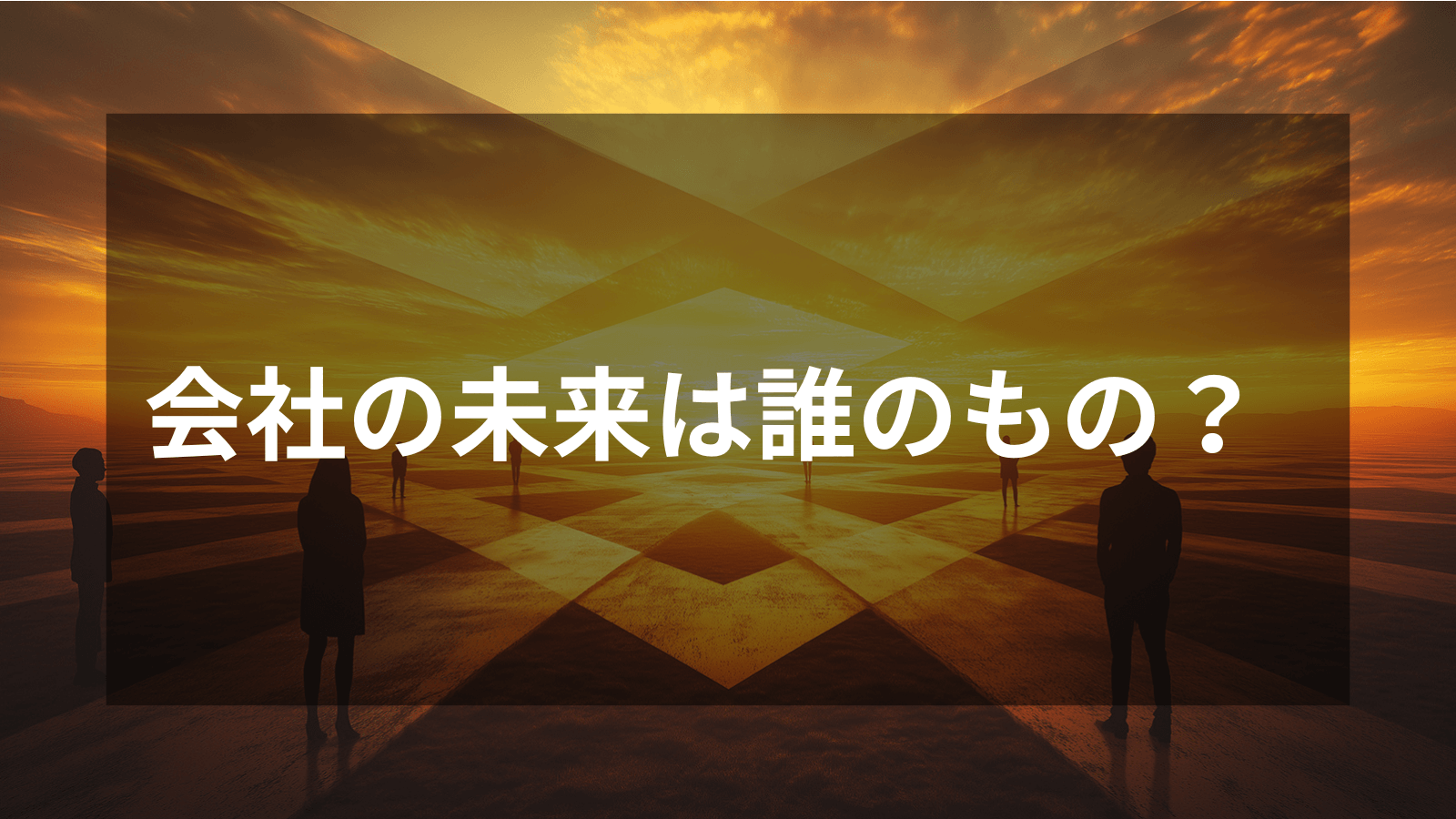特定贈与信託で実現する家族の安心設計
特定贈与信託とは何か
中小企業の経営者にとって、家族の将来を守ることは重要な責務です。特に、障害を持つご家族がいる場合、その方の生涯にわたる生活の安定を確保することは、経営者として、そして家族として最優先の課題となります。そんな経営者の皆様にとって強力な味方となるのが「特定贈与信託」という制度です。
特定贈与信託は、障害者の生活の安定を図ることを目的として、信託銀行等に財産を信託し、その信託財産から定期的に給付を受ける仕組みです。この制度は税制上の優遇措置が設けられており、通常の贈与であれば課税される金額でも、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となります。
具体的には、特別障害者の場合は6,000万円まで、特別障害者以外の障害者の場合は3,000万円までが贈与税の課税対象から除外されます。これは、障害者の生活の質を維持し、長期的な経済的安定を提供するための国の配慮と言えるでしょう。
制度の基本的な仕組み
信託の当事者
特定贈与信託には3つの当事者が関わります。
- 委託者:財産を提供する人(通常は経営者や家族)
- 受益者:給付を受ける障害者
- 受託者:信託財産を管理・運用する信託銀行等
中小企業経営者にとってのメリット
大幅な税負担軽減
通常、子どもに6,000万円を贈与すれば、贈与税は約2,840万円にもなります。しかし、特定贈与信託を利用することで、この贈与税負担をゼロにすることができます。これは経営者にとって非常に大きな節税メリットです。
信託された財産は、受益者である障害者の生活費、医療費、教育費等に充てるため、定期的に給付されます。この給付方法は、受益者の状況や必要に応じて柔軟に設定することができ、月額給付から年額給付まで様々な形態が可能です。
相続対策としての効果
経営者の財産から障害者の生活資金を予め分離しておくことで、相続時の財産総額を減らすことができます。これにより、相続税の負担軽減にもつながります。特に、事業用資産と個人資産が複雑に絡み合いがちな中小企業経営者にとって、財産の整理という意味でも有効な手段となります。
長期的な安心の確保
障害を持つ家族の将来への不安は、経営者の心の重荷となりがちです。特定贈与信託により、その方の生涯にわたる経済的基盤を確実に確保できることで、経営者は安心して事業に専念することができます。
専門的な財産管理
信託銀行による専門的な財産管理により、資産の保全と適切な運用が期待できるため、万が一受益者が亡くなった場合も、障害を持つご家族の将来へ備えることが可能です。
特定贈与信託を利用する際の注意点
契約できる金融機関の制限
特定贈与信託は、すべての金融機関で取り扱っているわけではありません。主に大手信託銀行(三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行等)で取り扱っています。一部の地方銀行や信託業務のみを専門に行う独立系信託会社でも扱っている場合がありますが、取扱機関は限られています。
地方の中小企業経営者の場合、身近に取扱機関がない可能性もあるため、事前の確認と相談が必要です。また、各機関により手数料体系や最低信託金額が異なるため、複数の機関で比較検討することをお勧めします。
信託金の管理代理人について
障害者本人が信託の管理や給付の受領を適切に行えない場合、代理人を立てる必要があります。
代理人として選択できる人
• 障害者の親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹等)
• 成年後見人
• その他信頼できる第三者
代理人選定の重要なポイント
• 障害者の利益を最優先に考えて行動できること
• 長期間にわたり責任を持って管理できること
• 信託銀行とのやり取りを適切に行えること
• 障害者の状況や必要を理解していること
代理人は将来的に交代する可能性もあるため、後継の代理人についても事前に検討し、家族内で話し合っておくことが大切です。
給付方法の慎重な検討
給付額や給付時期の設定は、障害者の生活パターンや必要経費を詳細に検討して決める必要があります。
• 月額給付:日常生活費をカバー
• 年額給付:まとまった支出に対応
• 臨時給付:医療費等の突発的な支出に対応
給付方法は後から変更することも可能ですが、変更手続きには時間と費用がかかるため、最初の設定が重要です。
障害者の状況変化への対応
障害の程度や生活状況は時間とともに変化する可能性があります。信託契約では、このような変化に対応できる柔軟性を持たせることが重要です。
実際の活用事例
ケース1:製造業A社社長の場合
A社の社長(60歳)は、知的障害を持つ長男(30歳)の将来を心配していました。特定贈与信託により5,000万円を信託し、月額15万円の給付を設定。これにより長男の生活費を確保し、相続財産も圧縮することができました。
ケース2:建設業B社社長の場合
B社の社長(55歳)は、身体障害を持つ次女(25歳)のために6,000万円の特定贈与信託を設定。信託財産の一部で障害者向け住宅を購入し、残りで生活費を賄う仕組みを構築しました。
手続きの流れ
事前相談
• 税理士・弁護士等専門家への相談
• 家族間での話し合い
• 信託銀行での制度説明
契約準備
• 必要書類の準備
• 給付方法の詳細決定
• 代理人の選定・確定
契約締結・信託設定
• 信託契約書の締結
• 信託財産の移転
• 給付開始
まとめ:経営者として考えるべきこと
特定贈与信託は、障害を持つ家族の将来を守りながら、相続対策としても効果的な制度です。しかし、制度の活用には以下の点での慎重な検討が必要です。
検討すべきポイント
• 信託金額と給付方法の適切な設定
• 信頼できる代理人の確保
• 取扱金融機関の選定
• 家族全体の相続計画との整合性
成功のカギ
• 早期の計画立案と実行
• 専門家との密な連携
• 家族間での十分な話し合い
• 定期的な見直しと調整
中小企業の経営者として、事業の発展と同様に、家族の幸せと安心を確保することも重要な使命です。特定贈与信託は、その両方を実現するための有効な手段となり得るでしょう。
制度の詳細や具体的な手続きについては、税理士や信託銀行の専門家にご相談いただき、ご家族の状況に最適なプランを構築することをお勧めします。障害のあるご家族の明るい未来と、経営者自身の安心のために、この制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
監修者

宮澤 博
税理士・行政書士
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、 お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、 他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。
無料相談のご予約・お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
(ソレイユ総合窓口となります)
0120-971-131
営業時間/平日9:00~20:00まで
※電話受付は17:30まで