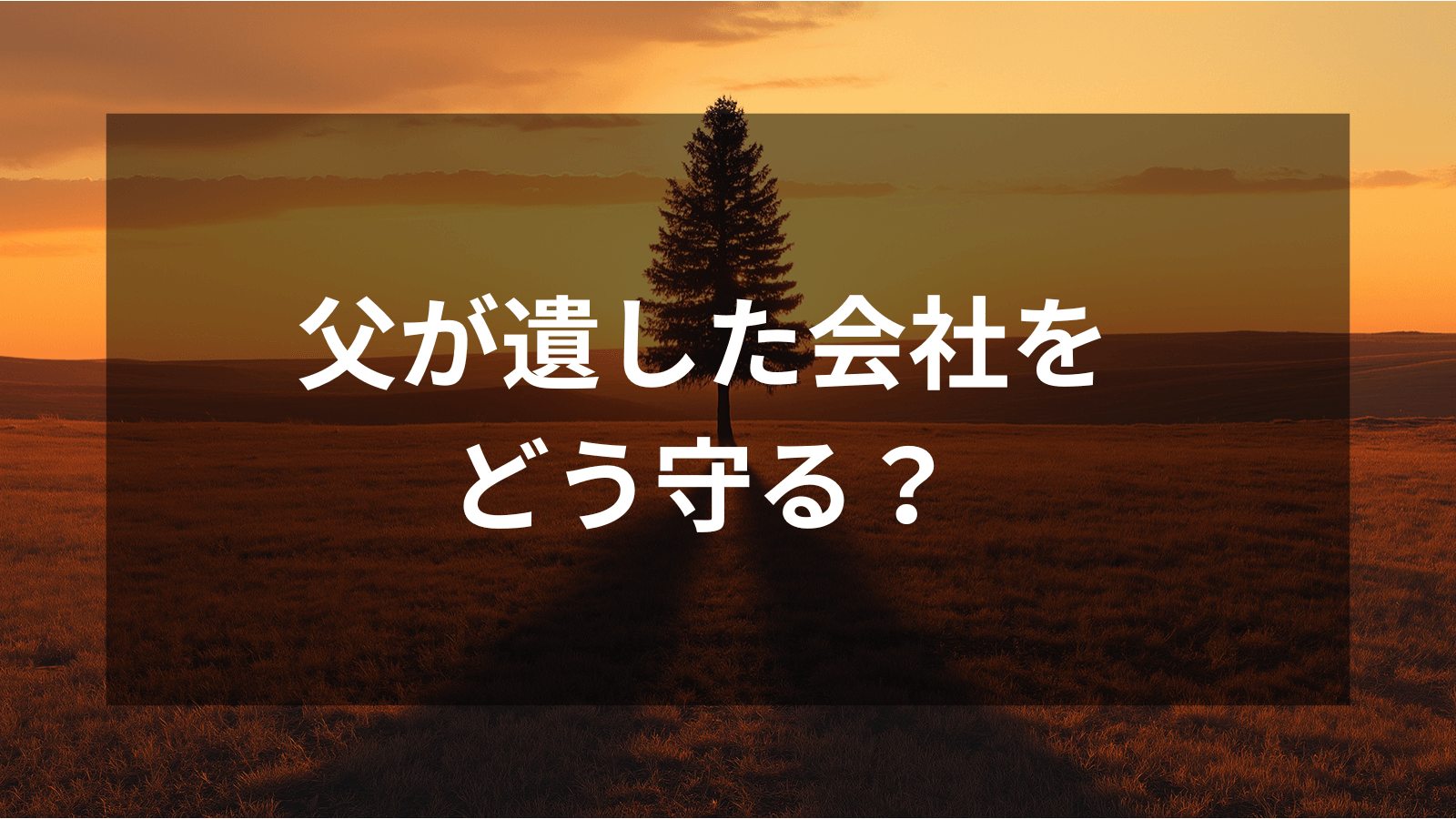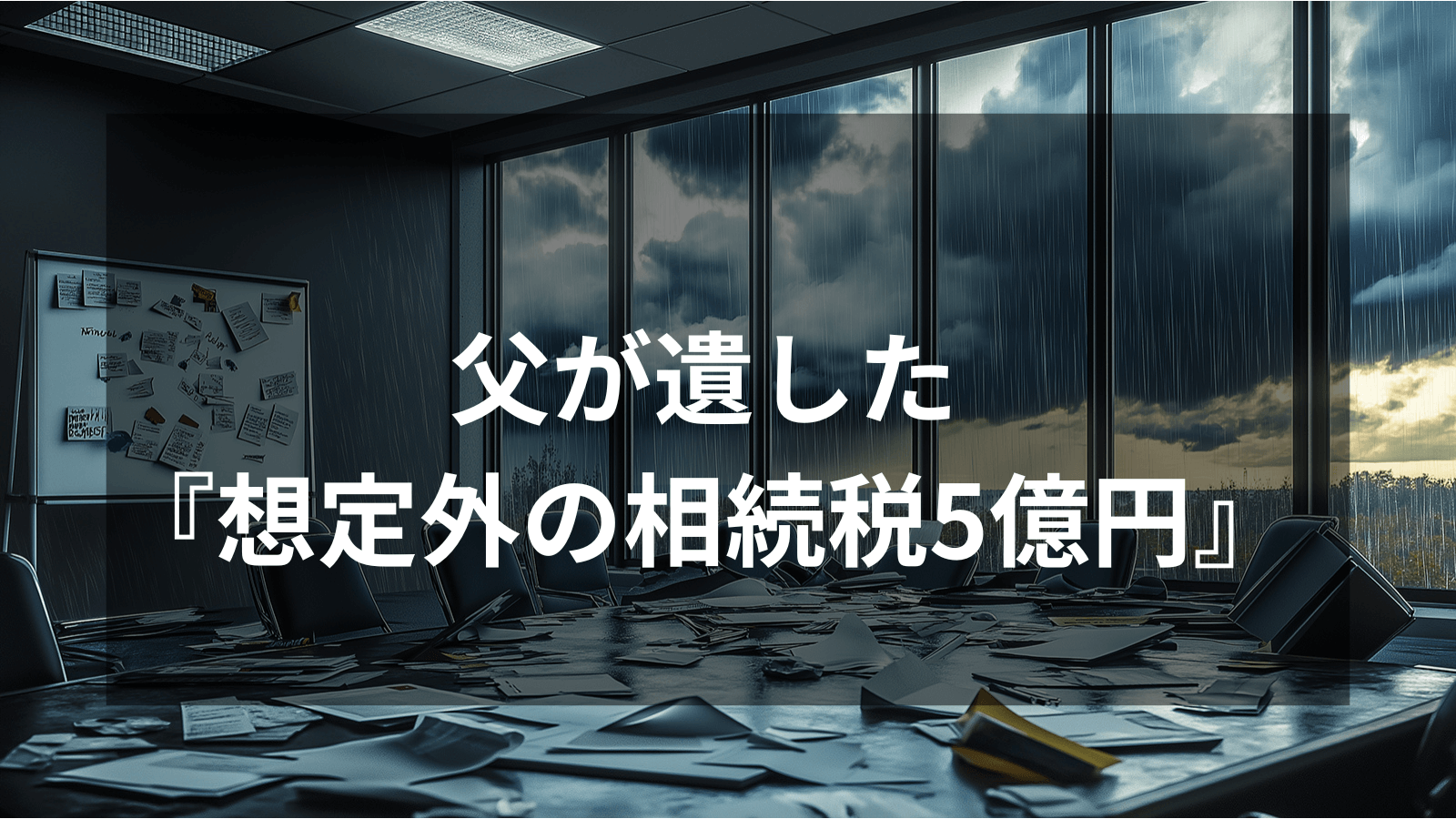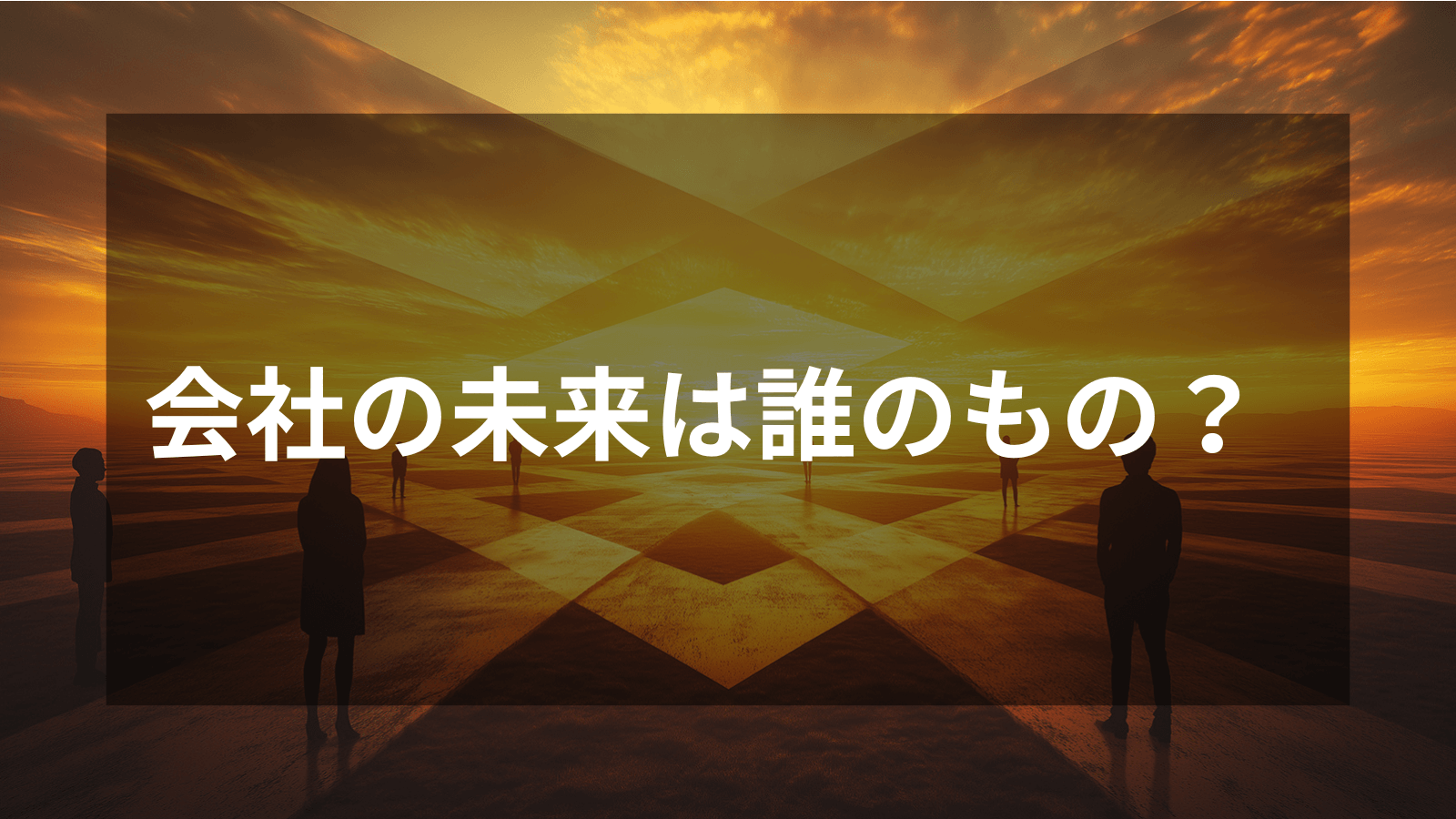<第三回>家族への財産の遺し方
法的手段の活用と特殊な承継パターン
はじめに
前回までの2回にわたって、財産の把握方法と具体的な遺し方について解説してきました。最終回となる今回は、これらの承継計画を確実に実行するための法的手段について詳しく説明します。家族信託や遺言といった基本的な手段から、従業員への財産承継、寄付活用まで、中小企業経営者が知っておくべき幅広いテーマを取り上げます。
家族信託の活用
家族信託とは何か
家族信託は、財産の管理・承継を目的として、家族間で行う信託です。認知症対策、事業承継、資産承継を一体的に解決できる制度として注目されています。これは証券会社に手数料を支払う商品ではなく、家族の間で契約を結ぶことができます。
家族信託では、財産を託し預ける人(委託者)、財産を管理し支払うことができる人(受託者)、財産を受け取り使うことができる権利がある人(受益者)という3つの立場があります。通常は経営者本人が委託者となり、信頼できる子どもや親族が受託者となって財産を管理し、経営者本人や配偶者が受益者として、契約に従って支払いを受けます。
認知症対策としての活用
経営者が認知症になった場合、会社の意思決定や自身の家庭の財産管理が停止してしまうリスクがあります。家族信託により、このリスクを事前に回避できます。
例えば、H社長(65歳)が長男を受託者として家族信託を設定したケースでは、自社株式の80%、収益不動産3物件、現金5,000万円を信託財産としました。この結果、H社長が認知症になっても長男が財産管理・会社経営を継続でき、H社長の生活費は信託財産から支出され、将来の相続時は信託契約予め定めた方法で承継されることになります。
事業承継における活用
事業承継において、経営権の承継と財産権の承継を分離して考えることで、より柔軟な承継が可能になります。自社株式を信託財産とし、受託者(後継者)が議決権を行使する一方で、受益権は複数の相続人に分割することで、議決権と配当をもらう財産権が分離できるのです。
また、配偶者が相続した財産の最終的な承継先を、あらかじめ信託契約で定めておく二次相続対策としても活用できます。遺言では次の相続で財産をもらう人しか指定できませんが、信託ならその次まで指定することも可能です。
家族信託設定時の注意点
家族信託を設定する際は、受託者の選定が重要です。信託事務を適切に遂行できる能力があり、受益者との利害関係を適切に処理でき、長期間の信託継続に対応できる人を選ぶ必要があります。
また、信託の目的の明確化、受託者の権限と義務の詳細な規定、信託終了条件の設定など、信託契約の内容も慎重に検討する必要があります。税務上も、信託設定時の贈与税の有無、信託期間中の所得税の納税義務者、信託終了時の相続税・贈与税の取扱いについて確認が必要です。
遺言の重要性と種類
なぜ遺言が必要なのか
中小企業経営者にとって遺言は、単なる財産分割の指針ではありません。事業の継続、家族の調和、従業員の雇用維持など、多面的な効果を持つ重要な手段です。
遺言がない場合、自社株が複数の相続人に分割されて経営権が不安定化したり、自社株の評価を巡って遺産分割協議が難航したり、事業に関係のない相続人が介入して事業承継が遅延するリスクがあります。
遺言の種類と特徴
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は費用が安く秘密性が高い反面、紛失・改ざんリスクがあり、家庭裁判所での検認が必要です。自筆遺言を法務局に保管してもらえる制度もありますが、内容の確認まではしてもらえません。一方、公正証書遺言は費用がかかり証人が必要ですが、紛失・改ざんリスクがなく検認も不要で確実性が高いため、複雑な内容や確実性を重視する場合に適しています。
事業承継における遺言の活用
事業承継では、後継者への自社株集中が重要です。遺言により「遺言者の有する○○株式会社の株式については、長男○○に相続させる」と明記し、さらに他の相続人が遺留分の主張を行わないことを希望する旨を記載することもできます。ただし、後継者には他の相続人に対する一定の金銭支払いを条件とすることで、公平性を保つことが重要です。
遺留分対策の重要性
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分です。配偶者・子が相続人の場合は法定相続分の2分の1、父母のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1が遺留分となります。
事業承継では、後継者に株式を集中させつつ、他の相続人の遺留分にも配慮する必要があります。遺留分に相当する現金等の準備、生命保険の活用、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)の活用などの対策が考えられます。
経営承継円滑化法では、後継者が贈与等により取得した自社株式を遺留分算定基礎財産から除外する除外合意や、その評価額を贈与時の価額に固定する固定合意が可能です。これにより、遺留分負担を大幅に軽減できる場合があります。
従業員に財産を遺したい場合
後継者への株式承継
血縁関係にない従業員や役員に事業を承継する場合、株式の有償譲渡、分割払い譲渡、無償贈与などの方法があります。有償譲渡は社長が対価を受け取れる反面、後継者の資金負担が大きくなります。分割払い譲渡は後継者の初期負担を軽減できますが、契約が複雑化し債権回収リスクもあります。無償贈与は後継者の負担はありませんが、贈与税の負担が発生します。
配偶者が使いやすい財産設計
信託の活用
配偶者が遺された財産を安心して使えるよう、家族信託の活用を検討しましょう。
家族信託とは 家族信託は、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、決められた人(受益者)がその利益を受け取る制度です。財産の「所有権」と「管理権」を分離することで、柔軟な財産管理と承継が可能になります。
社員持株会の活用
社員持株会は、従業員が共同で自社株式を取得・保有する仕組みです。毎月の給与から一定額を拠出し、会社からの奨励金も併せて株式を購入します。
事業承継における効果として、安定株主の確保による敵対的買収の防止、従業員のモチベーション向上、株式の分散による評価額の引き下げなどがあります。ただし、設立時は適切な株価の設定、売却制限の規定、退職時の取扱いの明確化などに注意が必要です。
寄付をしたい場合
公益法人等への寄付
社会貢献を目的とした寄付は、相続税の軽減効果も期待できます。国・地方公共団体、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに寄付した財産は、相続税の課税対象外となります。ただし、相続税申告期限内に寄付を完了する必要があります。公益法人等への寄付は、社会貢献と節税を両立できる有効な手段です。
一般社団法人の設立・活用
一般社団法人は設立が比較的容易で、公益認定を受ければ税制優遇も受けられます。事業承継においては、株式の承継先として活用したり、社会貢献事業の実施や雇用の維持・創出への貢献などに活用できます。
保証債務の整理と個人・法人財産の分離
経営者保証に関するガイドラインの活用
経営者保証に関するガイドラインでは、保証に依存しない融資の促進、保証債務の整理手続きの合理化、早期の事業再生支援が定められています。事業承継時には、先代経営者の保証債務の整理や後継者の新規保証の最小化、金融機関との交渉による保証免除などを検討できます。
個人財産と会社財産の分離
相続時の複雑化回避、税務上の問題防止、事業承継の円滑化のため、個人財産と会社財産の分離が重要です。個人名義の会社使用不動産の会社への売却、会社名義の個人使用不動産の個人への売却、個人・法人間の貸借の清算、適切な役員報酬の設定、賃貸借契約の適正化などを実行します。
実践的な承継スケジュール
事業承継は段階的に進める必要があります。承継3年前からの基盤整備段階では、財産の把握と評価、個人・法人財産の分離、後継者の決定と育成、基本的な生前贈与を開始します。承継2年前から1年前の本格実行段階では、事業承継税制の適用準備、本格的な自社株の移転、遺言書の作成、家族信託の設定を行います。承継1年前から承継時の仕上げ段階では、最終的な株式移転、役員の交代、契約関係の整理、アフターフォロー体制の構築を実施します。
まとめ
3回にわたる「家族への財産の遺し方」シリーズを通じて、中小企業経営者が知っておくべき相続・事業承継の知識を解説してきました。家族信託による認知症対策と事業承継の一体的解決、遺言による確実な承継と遺留分対策、多様な承継パターンへの対応、実務上の重要な準備など、総合的な視点が重要です。
中小企業の財産承継は、単なる税務対策ではありません。家族の幸せ、事業の継続、従業員の雇用、そして社会への貢献を総合的に考慮した、経営者の最後の重要な経営判断です。適切な準備により、これまで築き上げてきた財産と事業を確実に次世代に引き継ぐことができます。専門家と連携しながら、早期に、そして計画的に取り組むことが成功の鍵となります。
監修者

宮澤 博
税理士・行政書士
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、 お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、 他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。
無料相談のご予約・お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
(ソレイユ総合窓口となります)
0120-971-131
営業時間/平日9:00~20:00まで
※電話受付は17:30まで