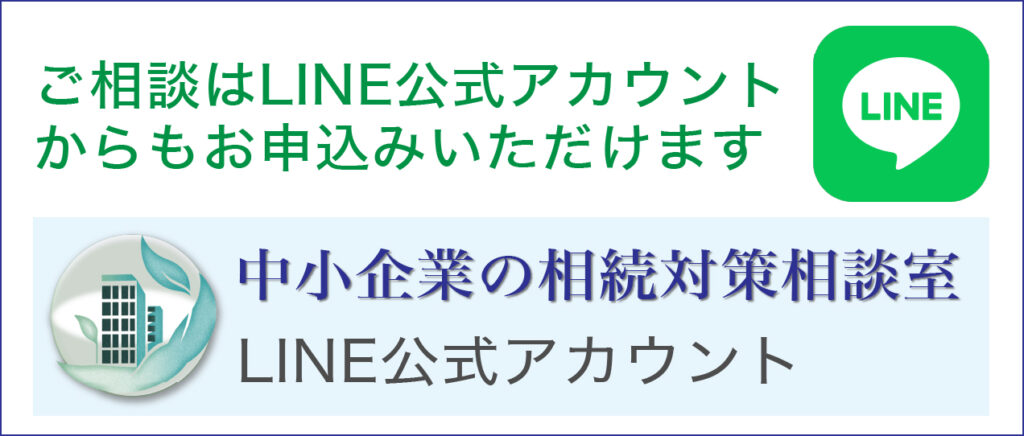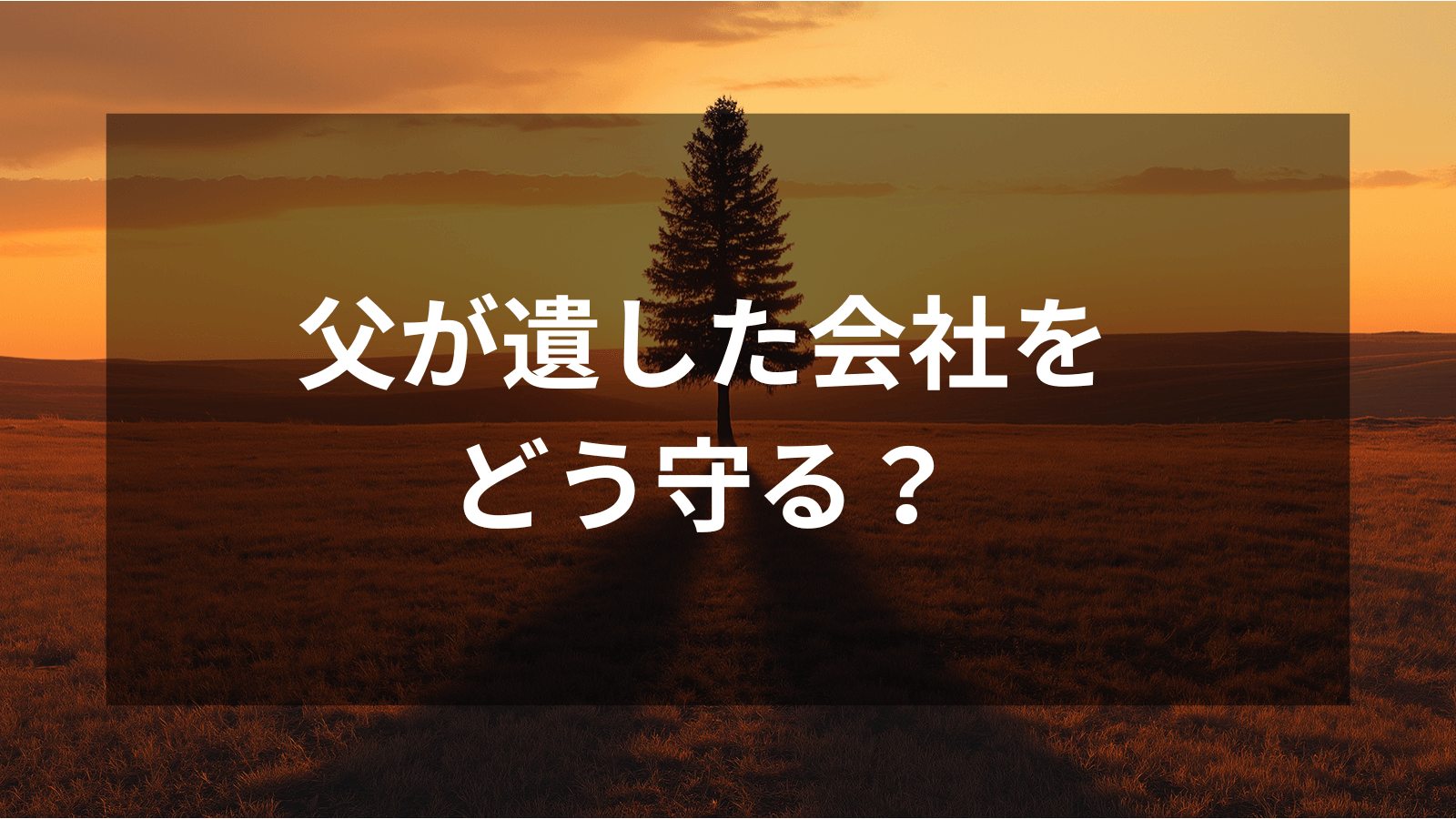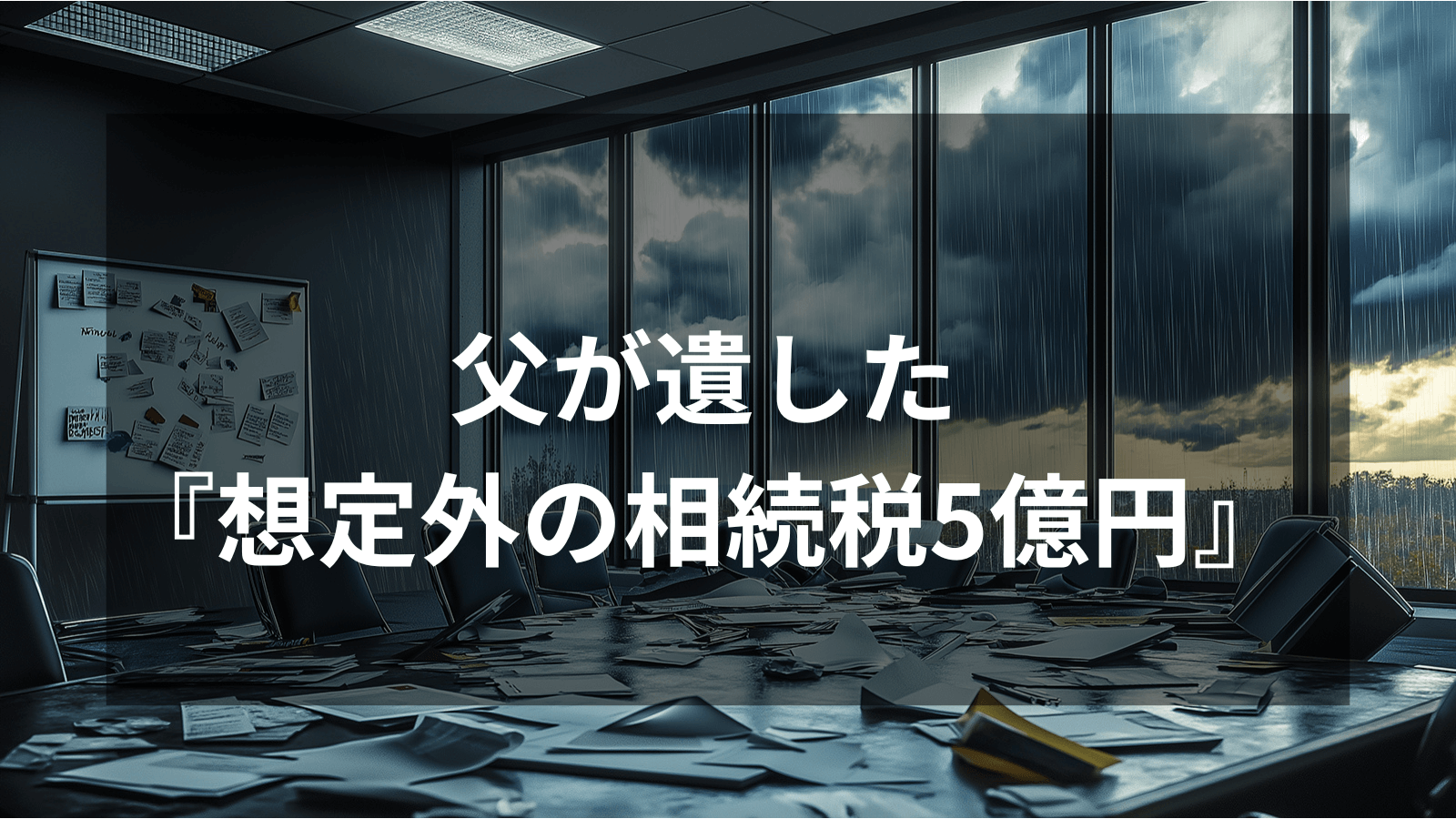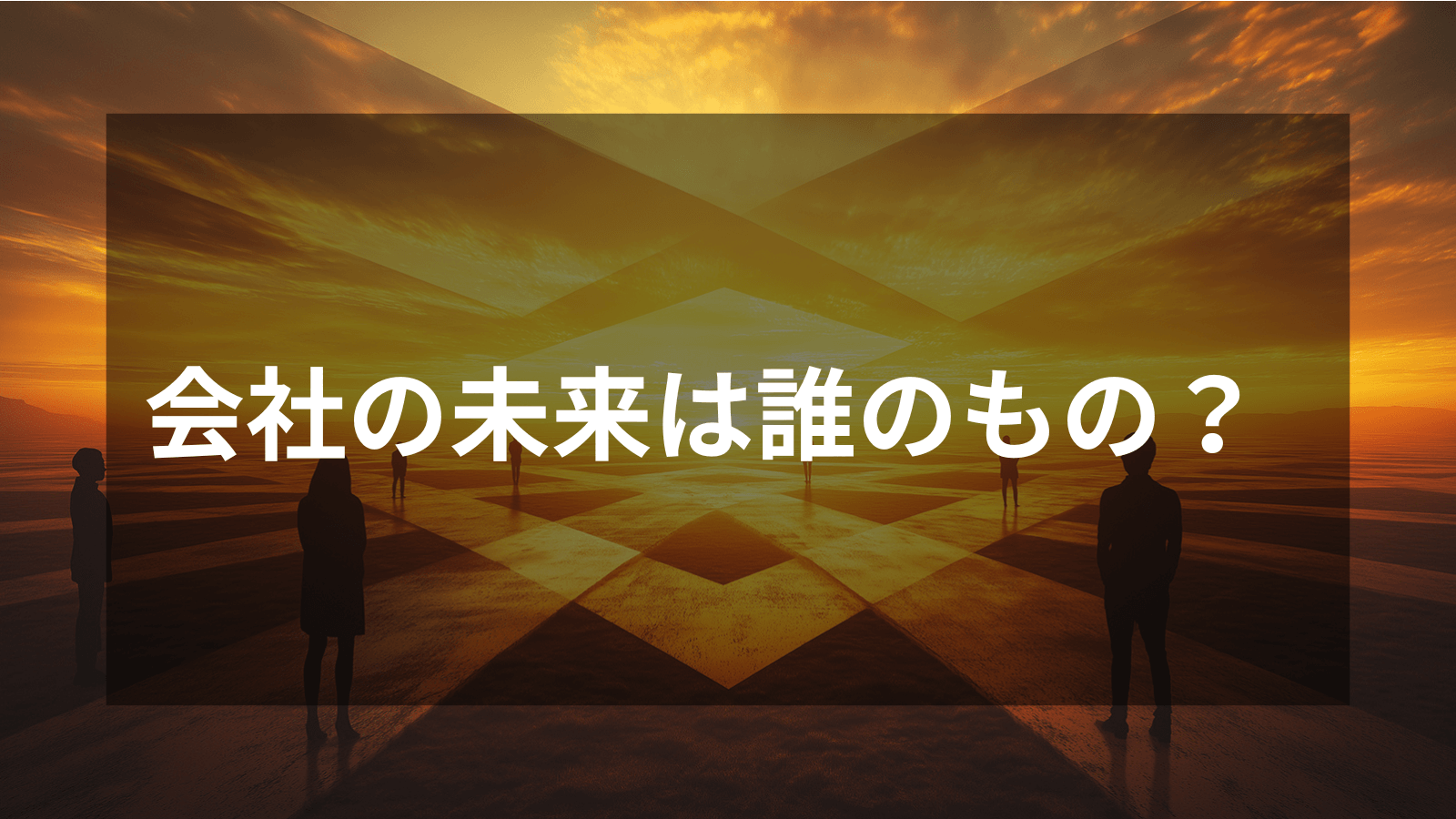<第二回>家族への財産の遺し方
財産の遺し方と生前贈与の戦略的活用
はじめに
第1回では、財産の全体像把握と相続税の基礎知識について解説しました。今回は、その把握した財産を「どのように家族に遺すか」という実践的な側面に焦点を当てます。中小企業経営者の場合、単純に財産を分割すれば良いというものではありません。配偶者の生活保障、事業承継、そして事業に関係のない子どもたちへの配慮など、複数の要素を総合的に考慮した戦略が必要です。
配偶者に対する財産の遺し方
配偶者への財産承継の重要性
中小企業経営者の配偶者は、長年にわたって事業を支え、時には経営にも関与してきた重要なパートナーです。経営者に万が一のことがあった場合、配偶者が安心して生活を送れるよう、適切な財産の遺し方を考える必要があります。
配偶者居住権の活用
令和2年に創設された配偶者居住権は、配偶者の居住の安定を図る重要な制度です。
配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた建物について、終身または一定期間、無償で居住し続けることができる権利です。
メリット
- 居住の安定確保:住み慣れた自宅に住み続けられる
- 相続税の節税効果:居住権と所有権に分割することで評価額が下がる
- 他の相続人への配慮:配偶者が居住権、子が所有権を取得することで、より多くの現金等を他の財産として分配可能
事例:配偶者居住権の活用例
D社長(70歳)の相続対策
・自宅評価額:5,000万円
・配偶者年齢:65歳
配偶者居住権の評価額:約2,000万円
建物所有権(居住権付き):約1,000万円
土地所有権:2,000万円
合計:5,000万円
従来の相続:配偶者が自宅全体(5,000万円)を相続
新制度活用後:配偶者が居住権(2,000万円)、長男が所有権(3,000万円)を相続
→ 配偶者の取得財産が3,000万円減少した分、他の財産を追加で相続可能
配偶者居住権設定時の評価額について
配偶者居住権を設定すると、権利が分離されるため、各権利の評価額の合計が元の不動産評価額と一致しない場合もあります。理由は主に以下の通りです。
- 評価方法の違い
• 配偶者居住権:居住権を設定する年数や自宅の築年数等を基に算定される
• 建物所有権(居住権付き):制約のある所有権として評価
• 権利分離により評価上の調整が生じる
- 実務上の特徴
• 個別の事情によって変動が大きく、合計が元の評価額を上回る場合も下回る場合もある
配偶者が使いやすい財産設計
信託の活用
配偶者が遺された財産を安心して使えるよう、家族信託の活用を検討しましょう。
家族信託とは 家族信託は、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、決められた人(受益者)がその利益を受け取る制度です。財産の「所有権」と「管理権」を分離することで、柔軟な財産管理と承継が可能になります。
- 家族信託による財産管理
o 委託者:経営者本人
o 受託者:信頼できる子どもや親族
o 受益者:経営者本人(存命中)→ 配偶者(経営者死亡後)
- 信託のメリット
o 認知症対策:経営者が認知症になっても受託者が財産管理を継続
o 遺産分割協議不要:信託契約により承継先が事前に確定
o 財産の使い道指定:配偶者の生活費、医療費など用途を具体的に指定可能
o 柔軟な承継設計:配偶者死亡後の財産の行き先まで事前に決定可能
生命保険の活用
相続税の支払いや配偶者の生活資金として、生命保険の活用は非常に有効です。生命保険金は相続財産とは別に、指定した受取人(配偶者等)に直接支払われるため、遺産分割協議の対象外となり、確実に財産を遺すことができます。
- 相続税納税資金の確保
o 相続税は現金での納付が原則
o 保険金により納税資金を確保
o 相続開始後、比較的短期間で現金化可能
- 非課税枠の活用
o 500万円×法定相続人数までは非課税
o 配偶者と子2人の場合:1,500万円まで非課税
o 非課税枠を超えた部分は相続税の課税対象
会社を継ぐ子どもがいる場合の財産の遺し方
事業承継における財産承継の考え方
事業を承継する子どもに対しては、会社の経営権を確保させつつ、他の相続人との公平性にも配慮した財産の遺し方が重要です。
事業承継税制の活用
一般措置と特例措置
事業承継税制には、一般措置と特例措置があります。特例措置は令和9年までの期間限定ですが、より手厚い支援を受けられます。
特例措置の主な内容
• 対象株式数:発行済株式総数の100%まで
• 納税猶予率:相続税・贈与税の100%
• 雇用確保要件:弾力化(雇用の8割を5年間維持 → 未達成でも理由があれば継続可能)
事例:事業承継税制の活用効果
E社長の事業承継(特例措置活用)
・自社株評価額:3億円
・後継者:長男(現専務)
・他の相続人:配偶者、次男
事業承継税制適用前の相続税
・自社株3億円に対する相続税:約1億円
・納税資金の確保が困難
特例措置適用後
・相続税の100%が納税猶予
・承継後5年間の事業継続により実質的な税負担ゼロ
・経営の安定化と雇用の維持を実現
相続時精算課税制度の目的と使い方
制度の概要
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、特別な課税方式を選択できる制度です。
制度の仕組み
特別控除額:2,500万円まで贈与税非課税
2,500万円超過分:一律20%の贈与税
基礎控除:令和6年より年間110万円の基礎控除も併用可能(制度改正)
相続時の精算:贈与財産は相続時に贈与時の価額で相続税の計算に含める
既納贈与税の控除:相続税から既に納めた贈与税を差し引き
従来との違い
令和6年の制度改正により、相続時精算課税を選択した場合でも、年間110万円までは贈与税・相続税ともに課税されない基礎控除が新設され、制度の使い勝手が大幅に向上しました。
事業承継での活用方法
- 自社株の贈与
o 会社の成長前に後継者に株式を移転
o 将来の株価上昇益を相続財産から除外
- 収益不動産の贈与
o 賃貸不動産を後継者に贈与
o 将来の賃料収入を相続財産から除外
活用時の注意点
• 一度選択すると以降の贈与はすべて相続時精算課税制度の対象になる
• 贈与時の価額で相続税を計算
• 相続税の方が税率が高い場合は不利になる可能性
事業に関係のない子どもに遺す財産
公平性の確保と生前贈与
事業を承継しない子どもたちにも、公平に財産を遺すことは重要です。ただし、自社株のように換金困難な財産ではなく、現金や収益不動産など、実際に活用できる財産を遺すことを考慮しましょう。
暦年贈与の活用
基本的な仕組み
暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの間に受けた贈与について課税する制度で、日本の贈与税制度の基本となっています。
制度の特徴
• 基礎控除:年間110万円まで贈与税非課税(受贈者1人あたり)
• 累進税率:110万円を超える部分は10%~55%の累進税率
• 贈与者・受贈者の制限:年齢制限なし、親族以外でも適用可能
• 相続財産からの除外:贈与から7年経過後は原則として相続財産に加算されない(令和6年1月1日以降の贈与から適用)
長期継続による大きな節税効果 暦年贈与の最大のメリットは、長期間継続することで大きな財産移転が可能な点です。また、相続開始前7年以内の贈与を除き(令和6年1月1日以降の贈与から適用)、贈与済み財産とその後の値上がり益も相続財産から除外されます。
効果的な暦年贈与の進め方
F社長の暦年贈与プラン(10年間)
・対象者:次男、長女、孫2人(計4人)
・年間贈与額:1人あたり110万円
・総贈与額:110万円×4人×10年間=4,400万円
・贈与税負担:ゼロ
・相続財産からの除外効果:4,400万円
暦年贈与の注意点
1.連年贈与の否認リスク
・毎年同じ金額、同じ時期の贈与は否認される可能性
・贈与の都度、贈与契約書を作成
・受贈者が財産を管理・運用することが重要
2.相続前7年以内の贈与
• 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される(令和6年1月1日以降の贈与から適用)
• 令和5年12月31日以前の贈与については、従来通り相続開始前3年以内のみが加算対象
• 延長された4年分(4年前~7年前)の贈与については、100万円まで相続財産に加算されない
• 3年以内の贈与は従来通り全額加算対象
例:6年前に300万円贈与した場合、200万円は加算されるが、100万円は加算されない
住宅取得等資金贈与の特例
子どもや孫の住宅取得時には、一般的な暦年贈与枠とは別に、非課税で贈与できる特例があります。
非課税限度額(令和6年)
• 省エネ等住宅:1,000万円
• その他の住宅:500万円
活用のメリット
• 高額な贈与が非課税で可能
• 子どもの住宅取得支援ができる
• 相続財産の減額効果が大きい
自分で自由に使えるお金の計算
ライフプランニングの重要性
財産を家族に遺すことも重要ですが、経営者自身が安心して引退後の生活を送るための資金も確保する必要があります。
必要生活資金の計算方法
現在の生活費の把握
- 基本生活費:住居費、食費、光熱費等
- 趣味・娯楽費:旅行、趣味活動等
- 医療・介護費:将来の医療費増加を見込む
引退後の必要資金計算例
G社長(現在60歳)のライフプラン
・現在の年間生活費:800万円
・引退予定年齢:70歳
・平均余命:85歳(引退後15年間)
必要資金の計算
基本生活費:600万円×15年=9,000万円
・医療・介護費:200万円×15年=3,000万円
・予備費・趣味費用:1,000万円
・合計必要額:1億3,000万円
確保済み資金
・役員退職金:5,000万円
・企業年金・厚生年金:3,000万円
・個人資産(生活用):3,000万円
・不足額:2,000万円 → 追加での資産形成が必要
生前贈与と自己資金のバランス
積極的な生前贈与を行う場合でも、自身の生活に必要な資金は確実に確保しておく必要があります。
- 優先順位の設定
o 第1優先:自身と配偶者の生活資金
o 第2優先:事業承継に必要な財産
o 第3優先:その他の子どもへの生前贈与
- 段階的な贈与計画
o 初期段階:余裕資金での小額贈与
o 中期段階:事業の安定化に応じて増額
o 最終段階:引退時期の確定後に本格的な贈与実行
生前贈与における実務上の留意点
- 贈与契約書の作成
o 贈与者・受贈者の署名捺印
o 贈与財産の特定
o 贈与の条件(あれば)
- 財産の移転
o 現金:銀行振込による送金
o 不動産:所有権移転登記
o 株式:株主名簿の書き換え
- 税務申告
o 110万円超の贈与:贈与税申告書の提出
o 特例適用時:適用要件の確認と申告
税務調査への対応
よくある指摘事項
- 名義預金の認定
名義預金とは、名義上は家族のものになっているが、実質的には被相続人(贈与者)が管理・支配している預金のことです。税務署は以下の点をチェックします。
o 通帳・印鑑の管理者
o 実際の財産使用者
o 贈与の認識の有無
- 定期贈与の否認
定期贈与とは、毎年決まった時期に決まった金額を贈与することが決まっている贈与のことで、税務上は最初の時点で総額を贈与する契約があったとみなされるリスクがあります。
o 毎年同額・同時期の贈与
o 総額をまとめて贈与したとの認定
o 契約書の不備
対策のポイント
• 受贈者自身による財産管理
• 贈与の都度の意思確認
• 適切な記録の保存
贈与税の計算と税率
贈与税の計算方法
暦年贈与の場合 (贈与財産の価額 – 基礎控除110万円)×税率 – 控除額
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例税率(直系尊属からの贈与)
20歳以上の子・孫への贈与には特例税率が適用され、一般税率より低くなります。
まとめ
第2回では、財産の具体的な遺し方と生前贈与の戦略的活用について解説しました。重要なポイントを整理すると
- 配偶者への財産承継
o 配偶者居住権の活用で居住の安定と節税を両立
o 家族信託による財産管理で認知症リスクに対応
o 生命保険で納税資金と生活資金を確保
- 事業承継する子どもへの対応
o 事業承継税制(特例措置)で税負担を大幅軽減
o 相続時精算課税制度で将来の成長益を除外
o 経営権の確保と他の相続人への配慮を両立
- 事業に関係のない子どもへの配慮
o 暦年贈与の長期継続で大きな節税効果
o 住宅取得等資金贈与で高額な非課税贈与
o 現金や収益不動産など実用的な財産の承継
- 自己資金の確保
o 引退後のライフプランに基づく必要資金の計算
o 生前贈与と自己資金のバランスある配分
o 段階的な贈与計画の策定
次回(第3回)では、これらの財産承継を実現するための法的手段として、家族信託、遺言、さらには社員への財産承継や寄付についても詳しく解説します。適切な法的手段を選択することで、家族の想いを確実に次世代に繋げることができるでしょう。
監修者

宮澤 博
税理士・行政書士
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、 お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、 他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。
無料相談のご予約・お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
(ソレイユ総合窓口となります)
0120-971-131
営業時間/平日9:00~20:00まで
※電話受付は17:30まで