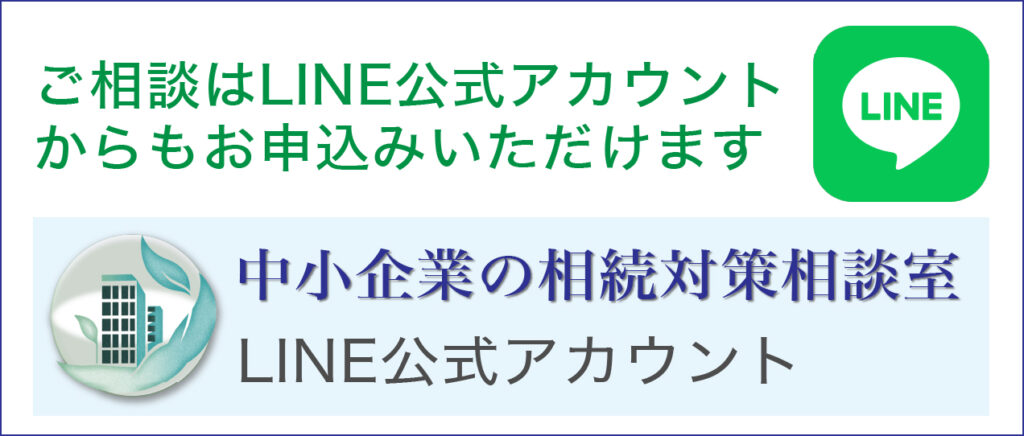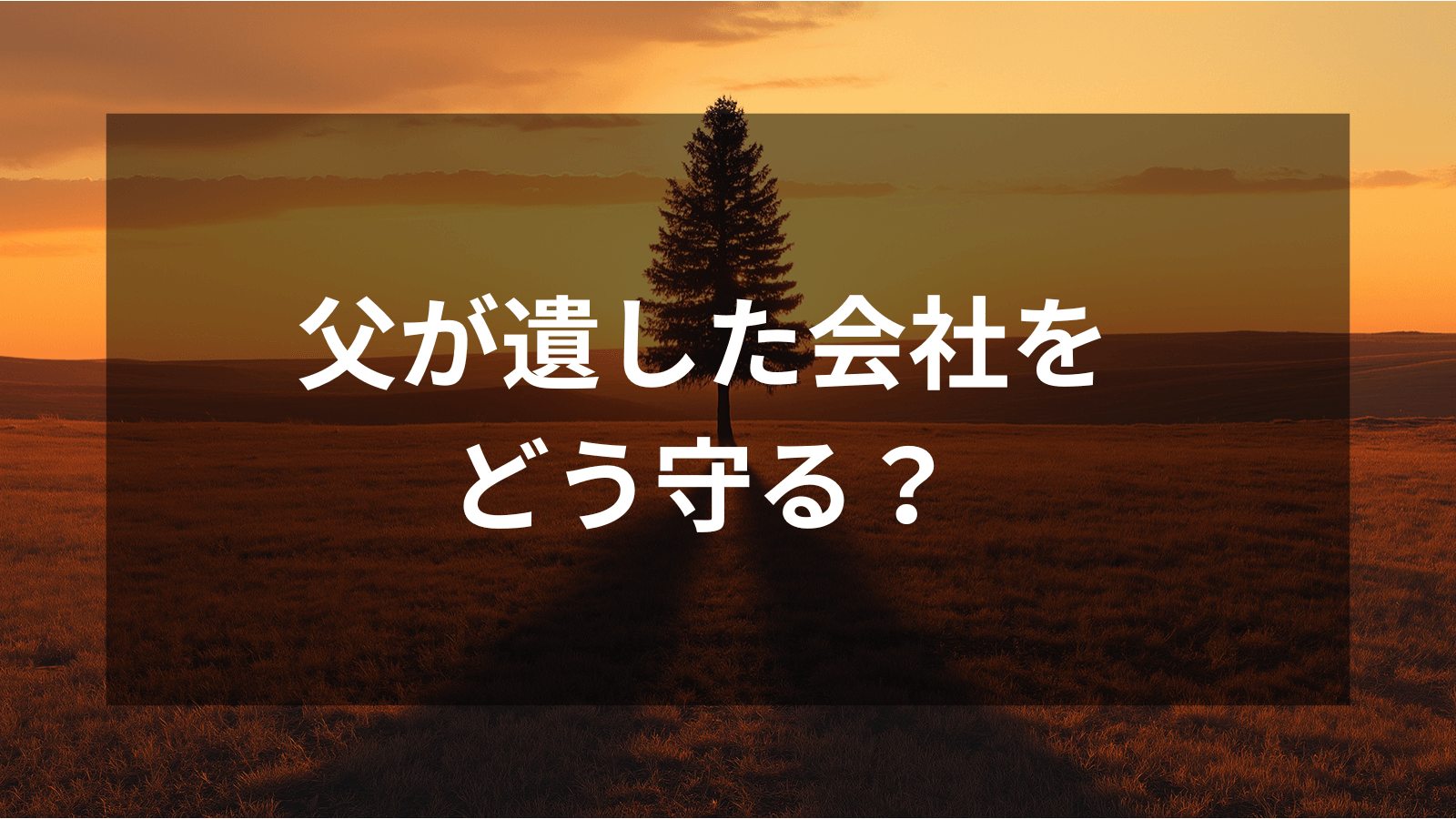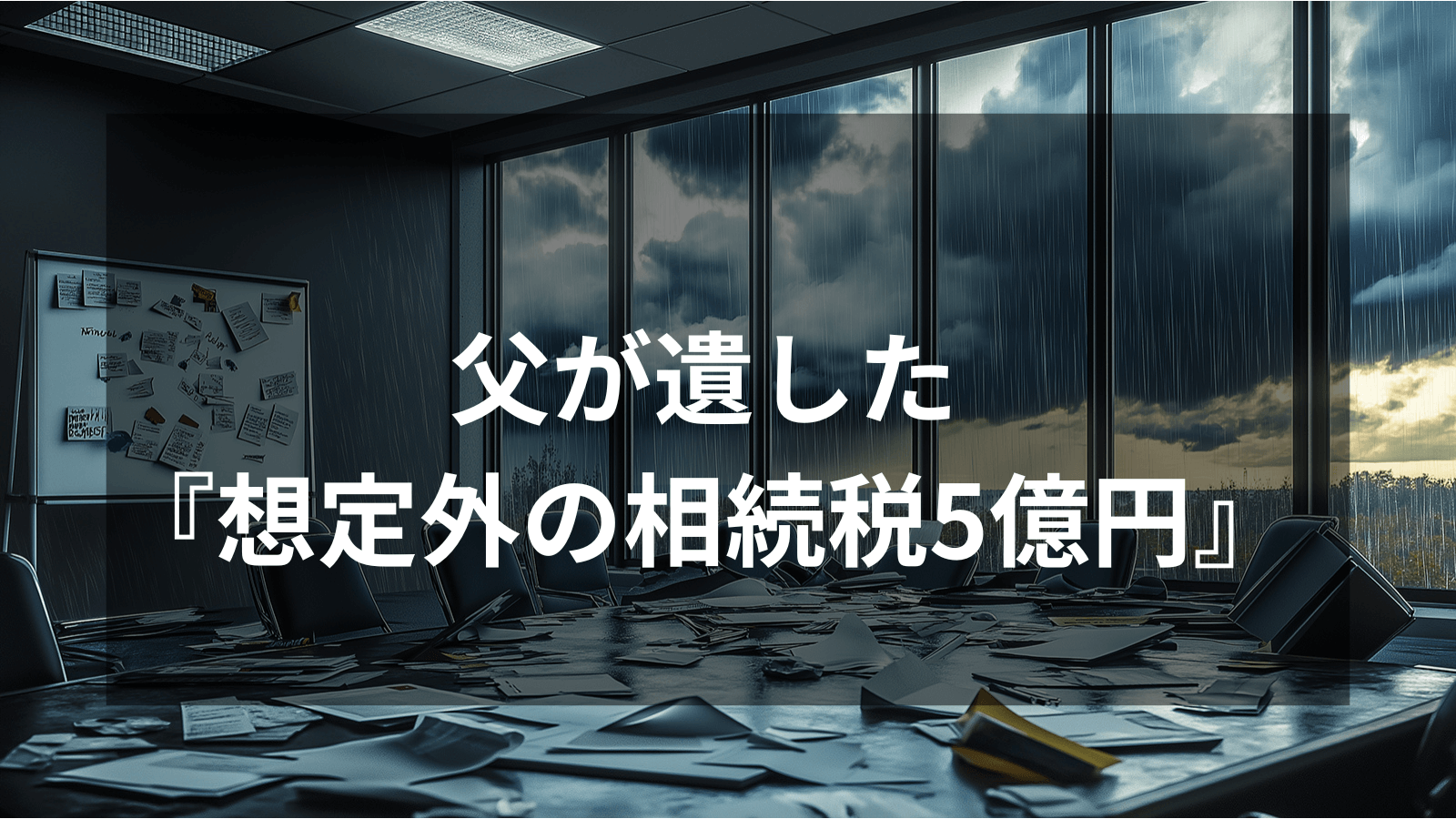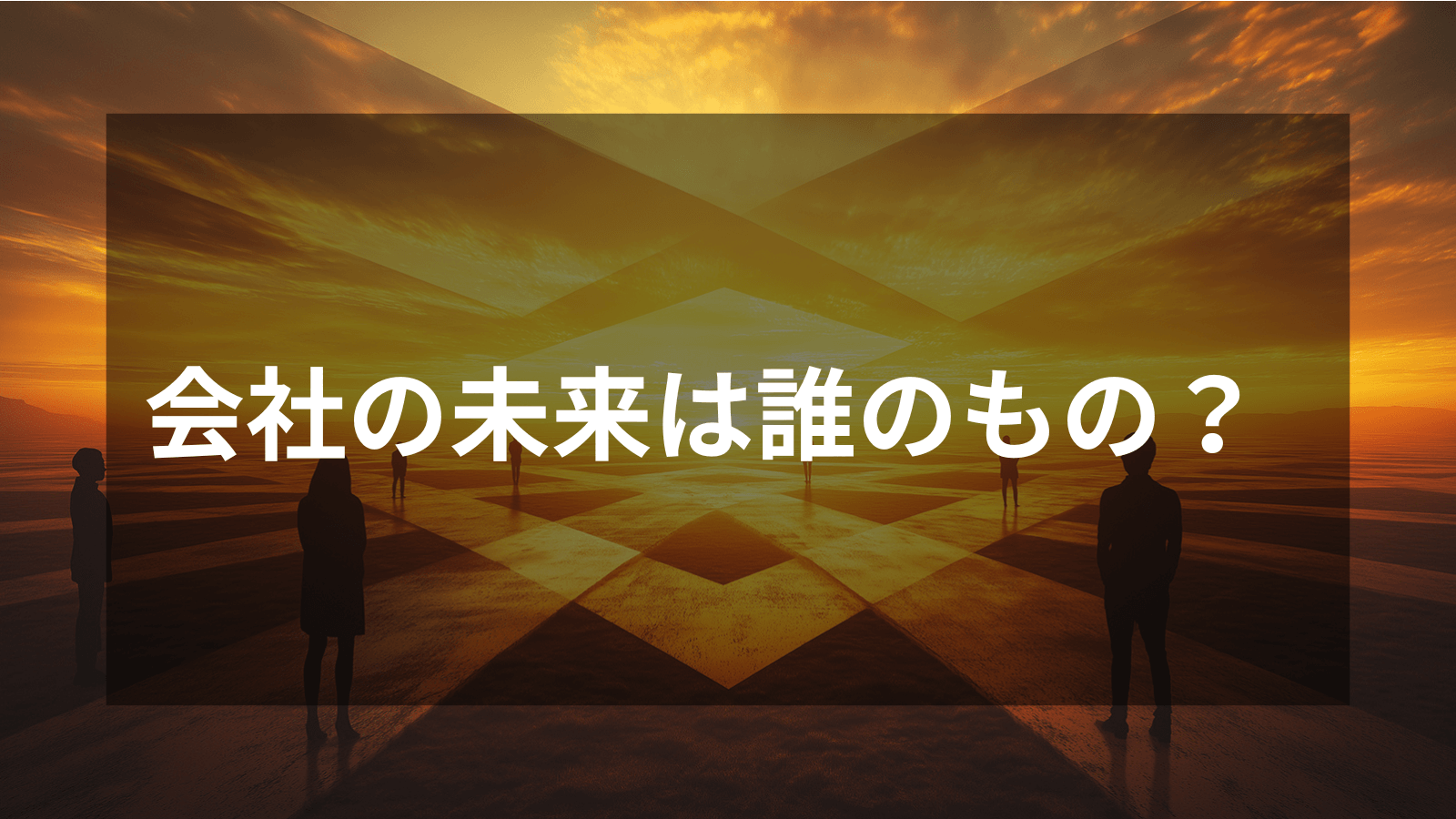<第一回>家族の安心から考える会社の相続対策
第一回:相続税は家族が払う税金
家族が背負う相続の現実
中小企業の相続対策を考える際、多くの経営者は「会社をどう継がせるか」という事業承継の視点に注目しがちです。しかし、実際の相続において税金を支払うのは、残された家族一人ひとりです。相続税は法人が支払う法人税とは異なり、個人が負担する個人の税金なのです。
この現実を理解せずに相続対策を進めると、思わぬ負担が家族にのしかかり、場合によっては家族の生活基盤を脅かすことになりかねません。本シリーズでは、家族の視点から中小企業の相続対策を考える重要性について、3回にわたってお伝えします。第一回となる今回は、相続税が家族にとってどのような意味を持つのか、具体的な事例を交えながら解説いたします。
相続税の基本的な仕組み:誰が、いつ、どのように支払うのか
相続税を支払う義務者は「相続人個人」
相続税は、被相続人(亡くなった方)から財産を相続した相続人が、それぞれ個別に支払う税金です。会社が支払う法人税とは根本的に性質が異なります。
相続税の基本的な計算方法
- 遺産総額から基礎控除額を差し引く
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人数
- 課税遺産総額を法定相続分で按分
- 各相続人の税額を計算
- 実際の相続割合に応じて税額を配分
申告・納税期限は「相続開始から10か月以内」
相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。この期限は延長することができず、遅れると加算税や延滞税が課されます。
中小企業経営者の相続における特殊性
個人財産と法人財産の境界があいまいになりがち
中小企業の場合、経営者個人の財産と会社の財産が密接に関わっていることが多く、相続時に複雑な問題が生じます。
よくある問題例
- 会社名義の不動産を社長が実質的に個人利用している
- 社長個人名義の不動産を会社が使用している
- 会社の借入金に対する個人保証
- 個人資産を会社の担保に提供している
自社株式の評価額が高額になるケース
中小企業の株式は、業績が良好な場合や不動産を多く保有している場合、相続税評価額が想定以上に高額になることがあります。しかし、これらの株式は市場で売却することが困難なため、現金化して相続税を支払うことは容易ではありません。
実際の事例から学ぶ相続税の現実
事例1:製造業A社の場合(従業員50名、年商8億円)
相続発生時の状況
- 被相続人:A社代表取締役(65歳で急逝)
- 相続人:配偶者(60歳)、長男(35歳・後継者)、次男(33歳・他社勤務)
- 主要財産:自社株式(評価額1億2,000万円)、自宅(3,000万円)、現金・預貯金(2,000万円)
相続税計算の結果
- 遺産総額:1億7,000万円
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税遺産総額:1億7,000万円-4,800万円=1億2,200万円
- 相続税総額:約2,000万円
この相続税額は、課税遺産総額1億2,200万円を法定相続分(配偶者1/2、長男1/4、次男1/4)で按分して計算した結果です。相続税の総額は、税法の規定により、法定相続分で按分した場合の計算によります。
各相続人の相続税額
- 配偶者:約350万円 ただし、配偶者控除により0円(自宅を相続)
- 長男:約1,400万円(自社株式を相続)
- 次男:約230万円(現金・預貯金を相続)
実際の相続では長男が自社株式1億2,000万円を、次男が現金・預貯金2,000万円、配偶者が自宅を相続したため、長男の支払い税額が取得財産の按分により大きくなりました。
二次相続への注意点
ここで重要なのは、配偶者が配偶者控除を利用して相続税を0円にした場合でも、将来の二次相続(配偶者が亡くなった時)に、配偶者が持っている財産が加算されるため、より大きな税負担が発生する可能性があることです。
二次相続では配偶者控除が使えず、相続人の数も減るため基礎控除額も小さくなります。そのため、一次相続で配偶者が多くの財産を相続し過ぎると、二次相続で子供たちにより重い税負担が課せられることになります。このA社の場合も、一次・二次相続を通算した税負担を考慮した分割方法の検討が必要でした。
家族が直面した問題
長男は会社を継ぐものの、自社株式は売却できないため、相続税1,400万円を自己資金で支払う必要が生じました。会社からの役員報酬だけでは納税資金が不足し、個人の住宅ローンの借り換えや生命保険の解約で資金を調達することになりました。
事例2:不動産業B社の場合(従業員15名、年商3億円)
相続発生時の状況
- 被相続人:B社代表取締役(58歳で病気により死去)
- 相続人:配偶者(55歳)、長女(28歳・会社員)、二女(25歳・専業主婦)
- 主要財産:自社株式(評価額8,000万円)、賃貸用不動産(6,000万円)、自宅(4,000万円)、現金(1,000万円)
特殊な事情
賃貸用不動産の多くが会社の借入金の担保に入っており、個人名義でありながら自由に処分できない状況でした。
相続税計算の結果
- 遺産総額:1億9,000万円
- 基礎控除額:4,800万円
- 課税遺産総額:1億4,200万円
- 相続税総額:約2,400万円
家族が直面した問題
配偶者は自社株式と現金を相続しました。配偶者は配偶者控除の利用により、相続税の負担はありませんでしたが、会社経営の知識がないため不安を抱えることになりました。長女と二女は賃貸用不動産を相続しましたが、会社の担保に入っているため、売却による納税資金の確保が困難でした。結果として、個人で金融機関からの借入によって相続税を支払うことになりました。
相続税が家族に与える深刻な影響
上記の事例からも分かるように、相続税は家族の生活に深刻な影響を与えます。最も大きな問題は納税資金の確保です。相続財産の多くが不動産や自社株式など現金化が困難な資産であるにも関わらず、相続税は現金での一括納付が原則となっています。
A社の事例では、長男が住宅ローンの借り換えや、生命保険の解約で納税資金を調達せざるを得ませんでした。B社では子供が借入による納税を余儀なくされました。これらは家族の将来設計に大きな影響を与え、教育費や老後資金の計画見直しが必要になります。さらに深刻なのは家族間の関係への影響です。相続税負担の不公平感や、会社経営への不安が家族の絆を脅かすことも少なくありません。
家族を守るために今すぐ始めるべき準備
こうした問題を回避するためには、事前の準備が不可欠です。まず重要なのは定期的な相続税額の試算です。自社株式の評価額は会社の業績によって変動するため、少なくとも年に一度は専門家による評価とシミュレーションを行うべきです。
そして試算結果を家族と共有することが極めて重要です。多くの経営者は「家族に心配をかけたくない」と情報を共有しませんが、いざ相続が発生した際の家族の衝撃と負担ははるかに大きくなります。定期的な家族会議で方針を共有し、各家族の希望や不安を把握することが円滑な相続対策の第一歩です。納税資金の確保には生命保険の活用が効果的で、計画的な生前贈与も重要な対策となります。
専門家チームによる総合的なサポートの必要性
中小企業の相続対策は税務、法務、財務など多岐にわたる専門知識が必要となるため、複数の専門家との連携が不可欠です。税理士は相続税の試算や節税対策の立案、事業承継税制の活用支援を行います。行政書士は遺言書の作成や家族信託の設計により相続トラブルを予防します。
司法書士は不動産の名義変更や抵当権の設定・抹消など、相続に伴う登記手続きをサポートします。これらの専門家が連携することで、経営者とその家族が安心して相続に備えることができるのです。
まとめ:家族の視点を忘れない相続対策を
相続税は、経営者個人だけの問題ではありません。残された家族一人ひとりが実際に負担する税金であり、その影響は家族の生活全体に及びます。
中小企業の相続対策を考える際は、以下の点を常に念頭に置くことが重要です。
- 相続税は家族が支払う個人の税金である
- 納税資金の確保は家族の生活に直結する問題である
- 事前の試算と準備が家族を守る最善の方法である
- 家族全員の理解と協力が不可欠である
- 専門家との連携により適切な対策を講じる
次回は「社長の保証債務は相続される」をテーマに、中小企業特有の保証債務の問題と、それが家族に与える影響について詳しく解説いたします。保証債務は相続税以上に家族の生活を脅かす可能性がある重要な問題です。ぜひ次回もご覧ください。
事例、人物、企業等の設定はフィクションです。
監修者

宮澤 博
税理士・行政書士
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、 お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、 他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。
無料相談のご予約・お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
(ソレイユ総合窓口となります)
0120-971-131
営業時間/平日9:00~20:00まで
※電話受付は17:30まで