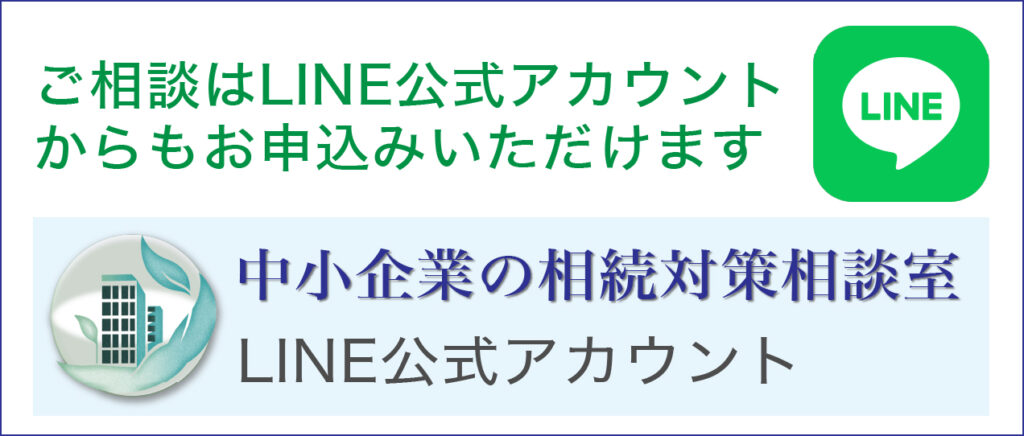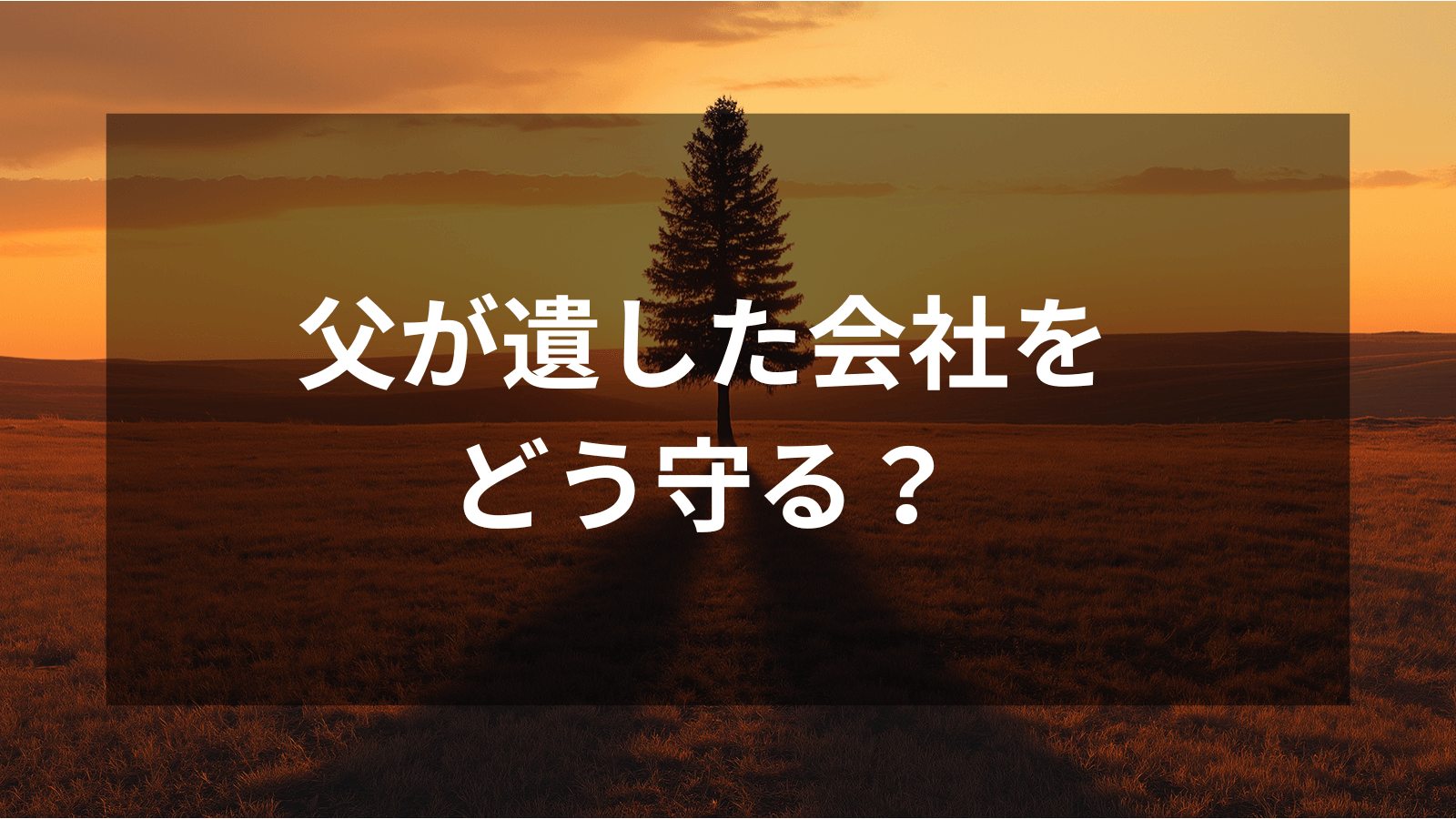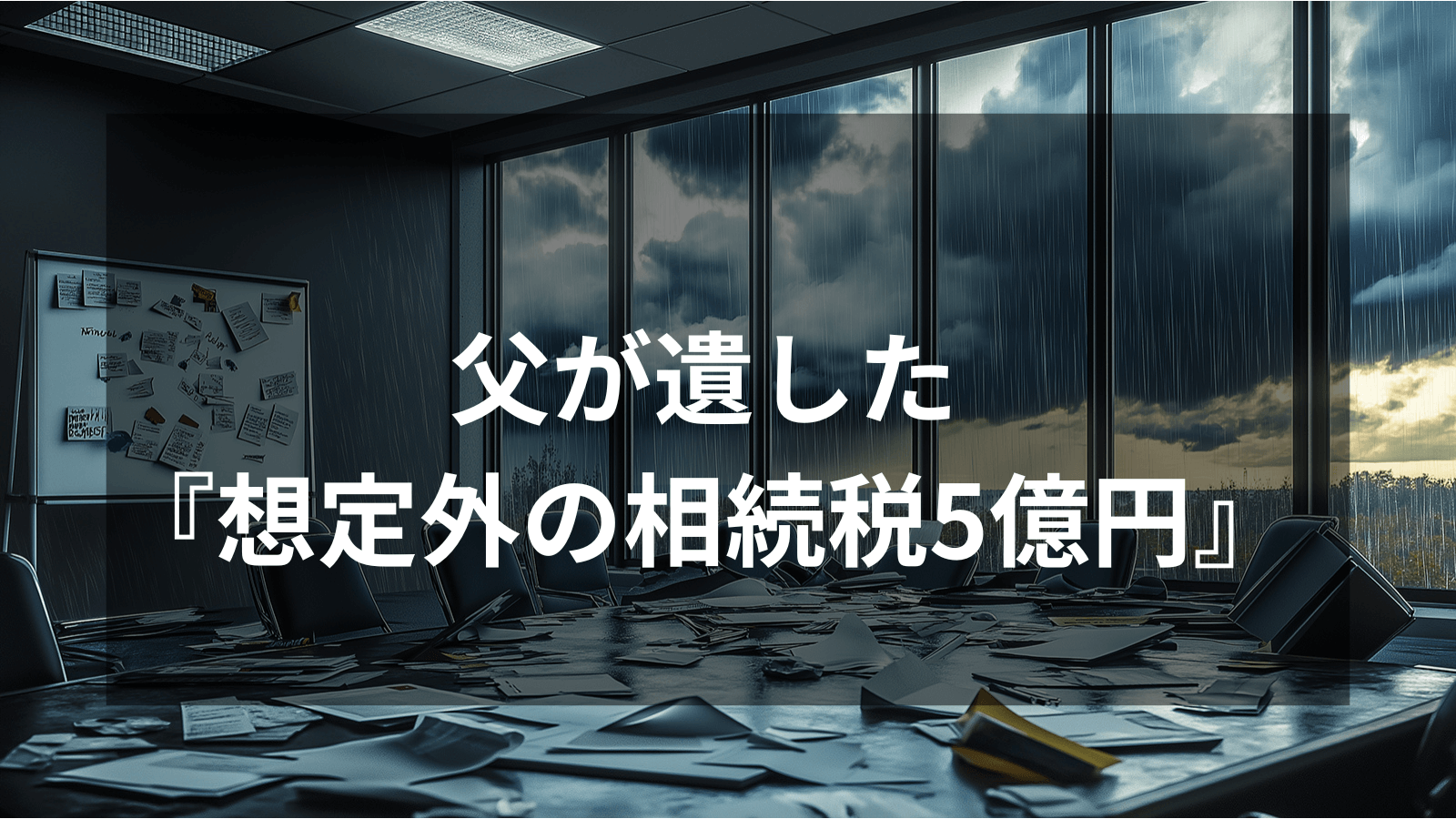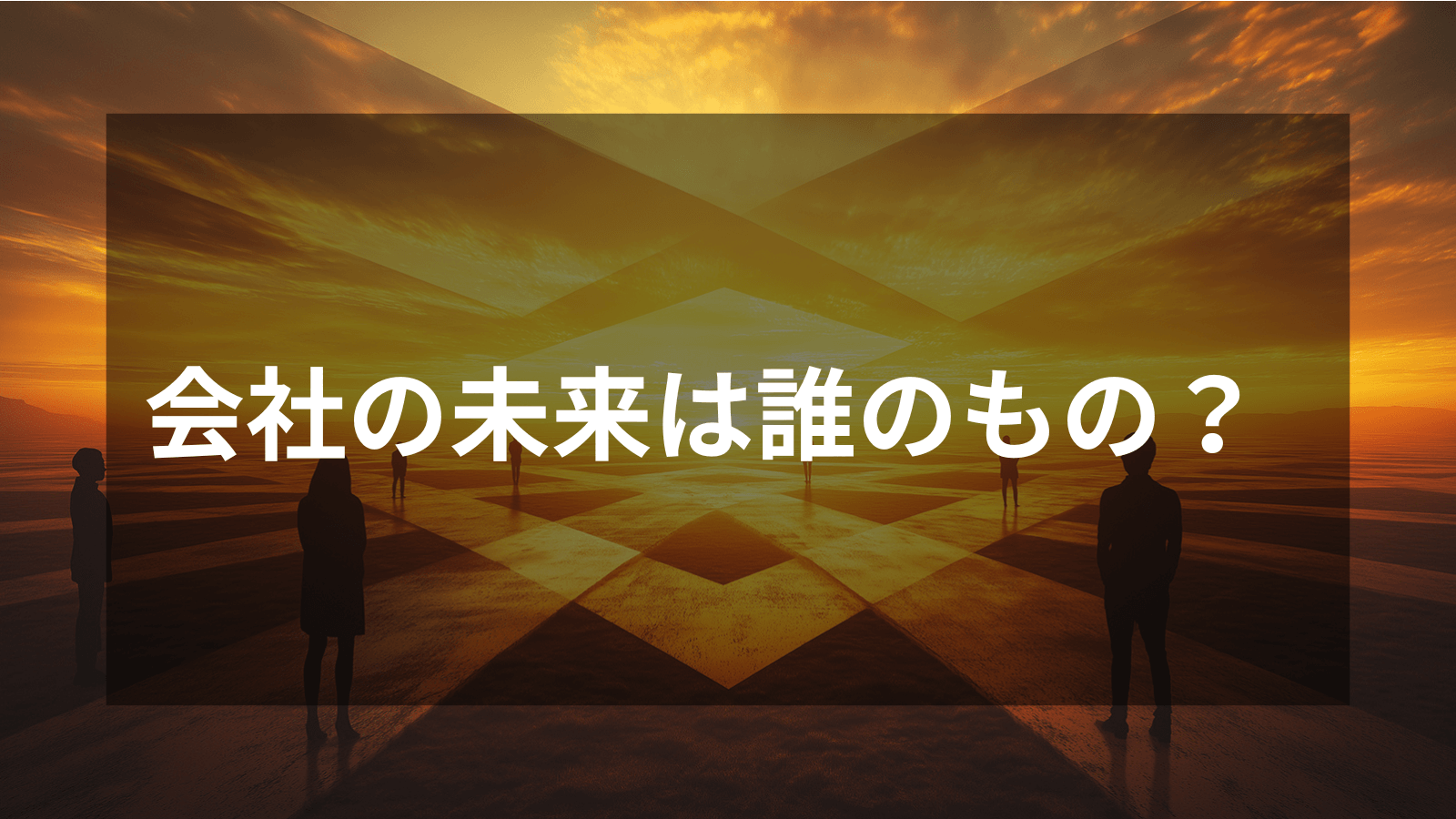自社株の評価額の値上がりを止める方法
1.はじめに:なぜ利益が出ると株価が上がるのか?
中小企業のオーナーが自社株をすべて保有しているケースは少なくありません。
この株価が毎年の利益によって上昇していくと、将来、相続税の大きな負担につながります。
評価額の上昇は、会社が順調に経営されている証でもありますが、放置すれば次世代の経営を圧迫しかねません。
そのため、「自社株の値上がりを抑える方法」を知っておくことは、事業承継対策の第一歩です
2.会社規模区分の判定からスタート
まず、自社株の評価額は「会社の規模」に応じて異なる方法で算出されます。
国税庁の基準では、会社規模は「大会社」「中会社(大・中・小)」「小会社」に分類され、業種、総資産、売上規模によって違ってきます。
【サービス業の場合の会社規模の目安】
中会社の小の例
- 売上高 2.5億円未満
- 従業員数 20人未満
- 総資産 2.5億円未満
※会社規模の判定は専門家の指導を受けるようにしてください。
3.事例 中会社の小の評価方法とは?
「中会社の小」に分類されると、株価は以下の式で計算されます。
自社株評価額 = 類似業種比準価格 × 60% + 純資産価格 × 40%
- 類似業種比準価格:同業他社の株価・利益・配当などの平均から算出される価格
- 純資産価格:会社の総資産から負債を控除し、株式1株あたりの価格に換算した額
業績が良く、毎年利益が出て内部留保が増えていくと、純資産価格が上がり、株価が押し上げられる仕組みです。
4.事例:利益が出ると株価が上昇するF社のケース
F社は、地域で展開する従業員20名のサービス業(売上2億円)。
代表取締役である社長(68歳)が全株式を保有しており、息子が専務として入社しています。
業績は安定しており、毎年500万円ほどの利益を出しています。
【評価年度の株価試算】
- 類似業種比準価格:1株あたり7.5万円
- 純資産価格:1株あたり10万円
- 評価額:7.5万 × 0.6 + 10万 × 0.4 = 8.5万円
社長の保有株数:1,000株 → 株式評価額:8,500万円
翌年、利益を1,000万円計上したことで純資産が増加し、1株あたりの純資産価格が11万円に上昇。
→ 新しい株価評価:7.5万 × 0.6 + 11万 × 0.4 = 8.9万円
→ 株式評価額:8,900万円(400万円アップ)
このように、会社が成長するたびに株価が自動的に上昇する構造になっています。
5.対策①:利益を調整して評価上昇を和らげる
評価額上昇の要因となるのは、内部留保=純資産の増加です。
以下のような経費を有効に使って、利益を調整することで純資産の増加をコントロールできます。
- 設備更新や車両購入(事業用資産)
- 教育研修費・福利厚生の強化
- 役員報酬・退職金制度の整備
- 役員賞・配当を行う
ただし、利益を抑えすぎると融資の評価に悪影響が出たり、純資産を減らす事で経営の健全性を損なう恐れがあるため、慎重な判断が必要です。
6.対策②:相続時精算課税制度で評価額を“固定”する
もっと根本的な方法は、自社株を評価が低い段階で生前贈与しておくことです。
このとき活用したいのが「相続時精算課税制度」です。
【制度の概要(令和6年以降)】
内容
贈与者/60歳以上の父母・祖父母
受贈者/18歳以上の子・孫(直系卑属)
非課税枠/2500万円(超過分は一律20%課税)
年間控除/110万円(令和6年から追加)
税金精算/相続時に贈与分を相続財産に加算して精算
特徴/贈与時点の評価額で固定できる
事例:相続時精算課税制度で900万円の評価上昇を回避
F社の社長は、株価評価が1株8.5万円の時点で、長男に500株を贈与(評価額:4,250万円)。
相続時精算課税制度を選択。 5年後、純資産が増え1株あたり11万円に上昇。
本来なら500株=5,500万円になるところ、贈与時点の評価額で固定されていたため、約1,250万円の相続税評価増を回避することができました。
もっと根本的な方法は、自社株を評価が低い段階で生前贈与しておくことです。
このとき活用したいのが「相続時精算課税制度」です。
7.専門家に相談すべき理由
自社株の評価には、「会社規模区分の判定」「純資産価格の計算」「評価方法の選択」など、複雑な専門知識が必要です。
さらに、相続税法・贈与税法・事業承継税制の改正が頻繁に行われており、最新情報のキャッチアップも不可欠です。
「うちの会社の評価区分は?」
「どのタイミングで贈与すべきか?」
「精算課税制度と暦年贈与どちらが得か?」
これらの判断は、税理士や事業承継に詳しい専門家に相談して初めて、適切な対策ができます。
8.まとめ:評価額が上がる前に対策を!
自社株の評価額が上がる理由を理解し、その上で評価額を抑える方法を考えることが重要です。
特に、相続時精算課税制度を活用することで、贈与時点の評価額で固定され、値上がりリスクを回避できます。
- 利益が出ている中小企業は評価額が上がりやすい
- 利益を出せば出すほど純資産が増え、株価が押し上げられる
- 利益を抑える工夫と、生前贈与で評価を固定することが有効
- 相続時精算課税制度は、将来の評価上昇を防ぐ最も確実な方法のひとつ
- 自社の状況に応じて、必ず専門家と対策を検討しましょう
【無料相談受付中】
相続時精算課税制度についてあなたの状況に合わせたアドバイスをお求めの方は
監修者

宮澤 博
税理士・行政書士
税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士
長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、 お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、 他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。
無料相談のご予約・お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
(ソレイユ総合窓口となります)
0120-971-131
営業時間/平日9:00~20:00まで
※電話受付は17:30まで